プリオケ31話は、りりとねずみ型アリスピアン・トーマの関係、そして白の女王の語る危うい理屈によって、アリスピアという世界の歪みがいっそう明確になる回でした。
プリンセスたちの正義は純粋ですが、その純粋さゆえに「理解が追いつかない他者」を前にすると、判断が乱れ、対話の糸口を見失ってしまいます。
一方で花の騎士側は情報を与えず、真実を語らないまま怒りや動揺で距離を置くため、衝突は避けようもなく深まっていきます。
特にりりの過去とトーマの消失を匂わせる描写は、これまでの価値観を揺さぶる重みを持っていました。
この回が示したのは、単なる敵味方の対立ではなく、「知らなさすぎる世界」に放り込まれたプリンセスたち自身の未熟さと、その向こう側にある痛みの物語です。
動画配信サイトのトライアル期間を使ってプリオケを全話無料視聴する方法と、解約時の注意点を別記事でまとめています。
- トライアル期間内に解約すれば課金されない
- 解約手順も事前に確認可能
りりが失ったアリスピアン、トーマ
31話がもっとも深い影を落としたのは、ねずみ型アリスピアン・トーマとりりの関係が一気に可視化された場面でした。
タブレットの動画に映るダンス好きのアリスピアン。
そしてOPに一瞬だけ映るシルエットのアリスピアン。
それらが白の女王の語りと重なり「りりがかつて親しくしていたアリスピアン」として、輪郭を得ていきます。
そして、それが同時にもう存在しないものとして語られてしまう。
断片的な情報の重ね方が、今回のエピソードに特有の痛みを生み出しています。
創作行為とアリスピアン
白の女王は言います。「強すぎるミューチカラはいずれ災いを招く」と。
ただし、ここで注意すべきなのは、アリスピアンが自ら強いミューチカラを生み出すわけではないという点です。
作中描写を丁寧に拾えば、アリスピアンはミューチカラを内側から生成できないか、もし仮にできてもごく微量にとどまることが推測できます。
これらの描写は、
- アリスピアンの肉体はミューチカラで構成されている
- 生命維持にミューチカラが必要
- アリスピアンにとって歌やダンスなどの創作行為は、文字どおり『身を削ること』になる
という可能性を示しています。
バンド・スナッチが演奏・歌唱しても消耗しなかったのは、
- 「一部の特別なアリスピアン」である
- 人の姿を得ている
- ジャマオックに近い存在になっている
- 赤の女王の力を分割して与えられている
などの要因が考えられます。
それでもなお、プリンセスの攻撃――すなわち、外部からの強すぎるミューチカラを浴びた結果消滅し、ミューチカラとなって赤の女王の元へ還りました。
そこから、アリスピアンは強力なミューチカラに触れると、肉体が維持できずに崩壊してしまう可能性も推測できます。
この前提に立つと、トーマに起きた出来事が見えてきます。
「好き」が命を削る|トーマがたどった結末
動画に映っていたトーマは、おそらく踊ることが好きだった。
しかし、アリスピアンの身体は歌やダンスといった、ミューチカラが絡む行為に耐えるようにはできていない。
- 自分の負荷で弱っていく
- 外部のミューチカラの衝撃はもっと危険
- バンド・スナッチと同じく、強いミューチカラに触れれば消滅し得る
つまりトーマは、自分が好きになった行為そのものによって、消えてしまう条件をつくってしまった
可能性があるのです。
りりが彼が消える瞬間を目撃していたとすれば、彼女が「歌やダンス」を遠ざけようとする態度は、単なる否定ではありません。
それは、「大切な相手が、自分の目の前で消えていく恐怖を二度と味わいたくない」という、切実な回避。
この痛みは、「アリスピアを守る責務」よりもはるかに個人的で、はるかに重いものです。
りりが抱えてきた沈黙の意味
りりはこれまで、拒絶の姿勢を貫いてきました。
しかし、それは冷たさでも無関心でもなく、喪失の記憶を抱えた子供が取る、もっとも自然な防衛反応だったのかもしれません。
トーマの消失は、プリンセスとの戦いや大義とは無関係に起きた、りり個人の人生の最初の悲劇。
その傷は、語られなかったからこそ深く、説明されなかったからこそ長く残った。
31話でトーマの存在が明かされた瞬間、りりの沈黙がはじめて物語の重さを持つ感情として読み取れるようになったのです。
プリンセスの正義の外側にあるもの
31話が示しているのは、プリンセスが守ってきた大きな物語とは別に、アリスピアンたちの世界には静かな痛みが積み重なっているという事実です。
その痛みはしばしば、外部から持ち込まれるミューチカラによって加速し、無自覚のうちに破壊を呼んでしまう。
だからこそ白の女王は「強すぎるミューチカラは災いになる」と言ったのかもしれません。
その言葉の是非はともかくとして、りりが抱えた喪失だけは、確かに災いの一形態だったのです。
プリンセスの「正義」の外側にある、小さくて個人的な痛み。
その存在を視聴者に突きつけた点で、31話は特に残酷なエピソードだったと言えます。
白の女王が語る危うい理屈と、プリンセスの知らなすぎる世界
第31話の核心は、白の女王とプリンセスの初めての真正面からの対話です。
これまで謎めいた存在として描かれてきた白の女王は、ようやく自らの口でアリスピアの「危機」を語ります。
しかし、この対話が明らかにしたのは単なる情報ではなく、双方の理解の浅さと、物語世界の構造的なズレでした。
白の女王が語る「強すぎるミューチカラ」問題
白の女王の主張は一見するとわかりやすいものです。
あなたたち、あちらの世界の人々のミューチカラは大きすぎる。強すぎる――。それはいずれ災いを呼ぶこととなる
引用元:『プリンセッション・オーケストラ』第31話
極端に言えば、「力が強すぎること自体が危険」という思想です。
しかしこれはすでに31話以前の描写から、りりの過去に関わる悲劇(トーマの喪失)と密接に関係している可能性が示唆されています。
白の女王の危機論は、ただの独善ではなく、過去の痛みや被害の上に立った思想なのかもしれません。
ただし、だからといって、その理屈が十分に説明されたわけではありません。
白の女王の語りは抽象的で、どこまでが事実でどこまでが彼女の主観なのかが曖昧なままです。
つまりこの時点では「危険性の指摘」だけが先行し、具体的な証拠は示されていない。
それが彼女の理屈を危ういものにしている最大の理由です。
プリンセスの理解と行動は食い違っている
対話の中で、かがりはこう問いかけます。
その言いよう、あなたも赤の女王と目的は同じなの?アリスピアのために動いているということ?
引用元:『プリンセッション・オーケストラ』第31話
この台詞は、白の女王の「彼女(赤の女王)のやり方では、アリスピアの未来は何も変わらなかったでしょうから」という言葉に対してものです。
かがりの問いは、以下のふた通りの解釈ができます。
- 白の女王は赤の女王と同じようにアリスピアのためと称して悪行を働いているのか?
- 白の女王は赤の女王と同じようにアリスピアを守ろうとしているのか?
白の女王が肯定した直後、ながせが「ちょっと待ってよ、全然そうなってないじゃん!」と追及したことから、かがりの意図が①だった場合、ここで矛盾が生じます。
したがって、かがりの問いの意図は②と判断されます。
だとすると、プリンセス側は「赤の女王もアリスピアを守ろうとしていた」と理解していたことになります。
24話の対話から本当に読み取れることだったのか
しかし、24話における赤の女王との対話を思い返せば、その解釈はかなり飛躍したものに見えます。
赤の女王は確かに「災い」を告げました。
しかしその語りは断片的で、プリンセス側が理解しきるには情報が圧倒的に不足していました。
事実、視聴者――というか、私の目には、プリンセスは「赤の女王はさらなる繁栄のためにアリスピアを弱肉強食の世界にしようとしている」と誤読しているようにすら映りました。
なぜプリンセスは踏み込まなかったのか
もし本当に赤の女王の目的を理解していたなら、代替案の提示も、継続的な対話も、危機の検証もなされていないのは不自然です。
アリスピアを守るための方法論の違いを議論する余地があったはずなのに、プリンセスはそこに踏み込むことなく赤の女王を倒し「問題解決」としてしまった。
このズレは、
- 脚本上の粗なのか
- プリンセスの「したくない現実から目を背ける幼さ」の描写なのか
判断が難しい部分です。
ただ、31話が露わにした「無理解の構造」を見る限り、後者(意図的な幼さの描写)として機能している側面も確かにあると言えます。
「あなたたちは何も知らない!」|プリンセスの浅い正義が突きつけられる
白の女王の抽象的な理屈に対し、プリンセス側もまた根本的に世界を知らなすぎます。
特にみなもが、
でも、ミューチカラはアリスピアを動かしてるエネルギーですよね? 大きくて強くて、いけないんですか?
引用元:『プリンセッション・オーケストラ』第31話
と困惑する場面は象徴的です。
普段から料理をしているのだから、「火力は強ければ強いほどいいわけではない」という感覚くらいは持っているはずですが、ミューチカラの過剰さが危険を生む可能性を、プリンセス側は一度も想像していなかった。
これが、ピュリティの激昂へとつながります。
「だから!あなたたちは何も知らないって言ってるんです!」
引用元:『プリンセッション・オーケストラ』第31話
本当にそのとおりで、プリンセスの価値観はあまりにも「アリスピア外部の論理」に偏っています。
アリスピアンと同じ目線の高さで世界を理解する試みが、この時点ではまだまったくできていないのです。
プリンセスの決めつけが生む齟齬|再び起きた価値観の衝突
ピュリティが「何も知らないくせに悪さって決めつけないでください」と返しながら、その「知られていないこと」の中身を語ろうとしない。
そして、かつてのバンド・スナッチもまた、自分たちの核心を明かさないまま消えていった。
この説明の欠落は、単なる脚本の粗ではなく、いくつかの構造が折り重なっているように見えます。
「悪いことしちゃダメ」は通じない|価値観の前提そのものが違う
31話で印象的なのは、リップルの次の言葉です。
そんなちっちゃいうちから悪いことしちゃダメなんだよ!
引用元:『プリンセッション・オーケストラ』第31話
これは、リップルなりの善意から出た言葉ですが──ピュリティは即座に「何も知らないくせに悪さって決めつけないでください」と反発します。
この応酬は、20話のミーティアとベスのやり取りを自然と思い出させます。
「あんたたちみたいな悪いやつら」「お前たちが正義だとなぜ言い切れる?」という、価値観の押し付け合い。
今回も同様に、相手の行動を「悪」と断じるプリンセスの言葉が、ピュリティの怒りを引き起こす構図となっていました。
しかも、ピュリティは小学5年生で、中学2年生のリップルと3歳しか離れていない。
それなのに「ちっちゃいうち」と幼児扱いするズレが、プリンセスが「相手を一段下に見る」癖として露わになっています。
これは、25話の主人公であり31話でも再登場したぼたんが、5歳児のあさぎを対等なパートナーとして扱っていることと対照的です。
20話・21話から続く「一方的な言葉のぶつけ方」
この衝突は、突然生まれたわけではありません。
20話・21話で既に兆候がはっきり描かれていました。
20話
- ミーティアがベスを「悪いやつ」と断じる
- ベスは「お前たちが正義だとなぜ言い切れる?」と反論
→価値観そのもののすれ違いが露呈した回
21話
- ドランが「本当にアリスピアを歪めているのはお前たちなんじゃないのか?」と指摘
- プリンセスはその言葉の意味を受け止められず対話は決裂
→「自分たちの影響」という視点が欠落していることが示唆された回
そして31話
リップルの台詞は、この流れを踏まえれば自然な延長線上にあります。
相手を理解する前に、「悪いこと」と断じる。
説明を求める前に、「正しさ」を主張する。
こうしてプリンセスは、「対峙した相手の扉」をまた閉ざしてしまいました。
それでも「語られない」のはなぜか|花の騎士とバンド・スナッチに共通する沈黙の構造
ピュリティの「何も知らないくせに」という怒りは、ただの反抗ではありません。
その後も彼女は事情を説明しようとしません。
この「語らなさ」は、バンド・スナッチや赤の女王と同じ構造を持っています。
以下では、この沈黙を三層の視点から整理します。
① キャラクター心理|「語れば傷が開く」から語れない
りりは、トーマを失った可能性を含め、非常に痛みの大きい経験を抱えています。
- トーマと共有した幸福
- その末に起きた破局
- 自分が花の騎士側に立っている理由
これらは「状況説明」ではなく「心の傷」の領域です。
語ること自体が痛みを伴うからこそ、りりは沈黙する。
この構造は、18話~21話のバンド・スナッチとも同じです。
語れば壊れる/語っても伝わらない──その危うさを知っている者の沈黙です。
② 情報の分断|真実を知る者は極端に限られている
一般アリスピアンはアリスピアの深層構造を知りません。
- ナビーユでさえ女王の存在を知らなかった
- 地球の少女との共存を疑いなく肯定している
- ミューチカラの危険性も共有されていない
つまり、アリスピアの社会は徹底的に情報が分断された世界です。
真実を知っているのはふたりの女王とその配下と、ごく限られた層だけ。
りりが語るという行為は、プリンセス個人への説明ではなく、アリスピア全体の情報秩序を崩壊させる行為になりかねない。
だからこそ、花の騎士は沈黙せざるを得ない面があります。
③ 物語構造|「語られなさ」が物語を成立させている
物語論的に言えば、この作品は一貫して「真実にたどり着けない構造」で進んでいます。
- バンド・スナッチも真実を語らなかった
- 赤の女王も断片だけ提示
- 白の女王も肝心な部分は伏せる
- りりも核心に触れない
この断片だけ落とす語り方によって、プリンセス側の「無理解のまま前進」が成立します。
もしこの瞬間にりりが全てを語れば、プリンセスの成長物語も、花の騎士の暗部も、女王の思想対立も、すべて終わってしまう。
りりの沈黙は、物語の駆動力として必要な空白でもあるのです。
その一方で、そういった作り手の都合が透けて見えるのは視聴者の興を削ぎます。
決めつけは、無意識の「力の行使」である
31話は、プリンセスたちが「相手の行動をすぐ『悪』と断じる癖」をまたも浮き彫りにしました。
これは単なる言葉の乱暴さではなく、相手の声を奪う「無意識の支配」として機能してしまいます。
一方で、花の騎士は、語れば壊れる/語れば秩序が崩壊するという理由から沈黙を選ぶ。
つまりこの世界は、語れない側と決めつける側の不均衡によって衝突が起こるように設計されている。
その構造が、今回の価値観の衝突を避けがたいものにしたのです。
まとめ|語られない真実と決めつける正義が生む断絶
プリンセスたちは、相手を理解する前に善悪の枠にはめてしまう「決めつけ」の癖を抱えており、それが花の騎士との対話をたびたび行き詰まらせています。
一方で花の騎士側は、痛み・情報統制・物語構造といった複合的な理由から、核心を語らない姿勢を崩しません。
この「語れない側」と「決めつける側」の不均衡が、価値観の衝突を避けがたいものにしています。
31話は、双方の立場の違いを鮮明にすることで、アリスピアの歪んだ構造そのものを浮かび上がらせました。
そして物語は、プリンセス自身が「知らなさすぎる世界」とどう向き合うのかという、本質的な問いへ向かい始めています。
動画配信サイトのトライアル期間を使ってプリオケを全話無料視聴する方法と、解約時の注意点を別記事でまとめています。
- トライアル期間内に解約すれば課金されない
- 解約手順も事前に確認可能
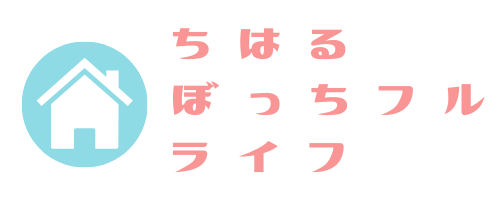
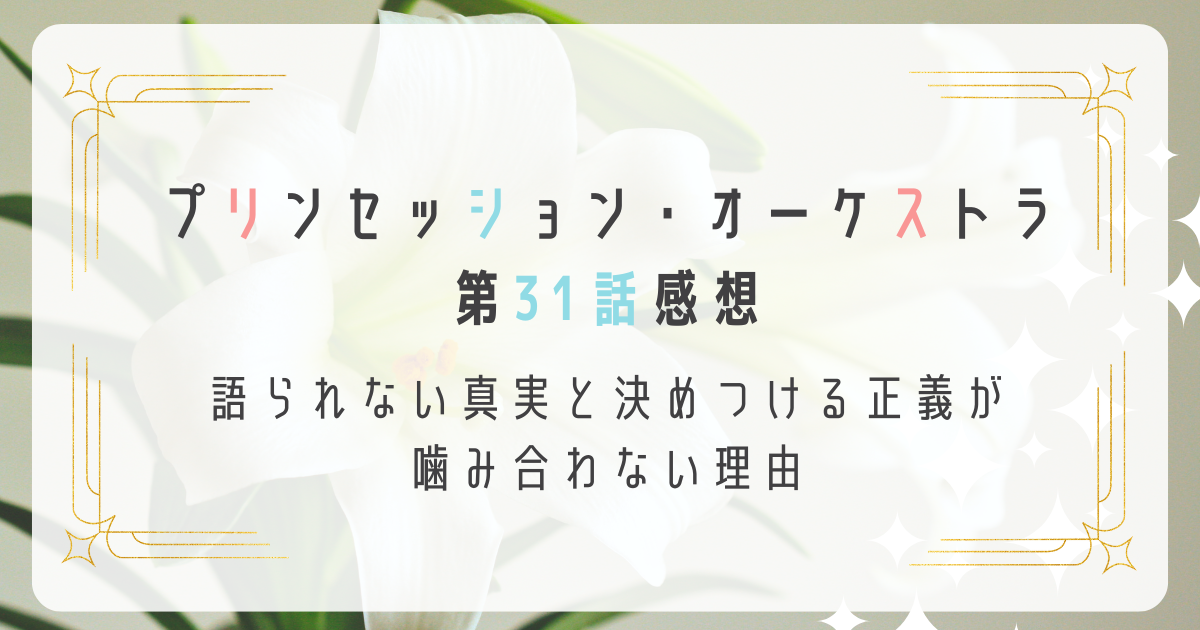
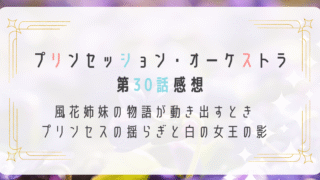

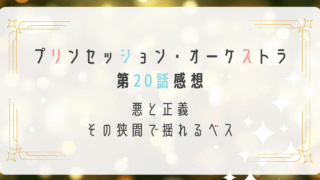
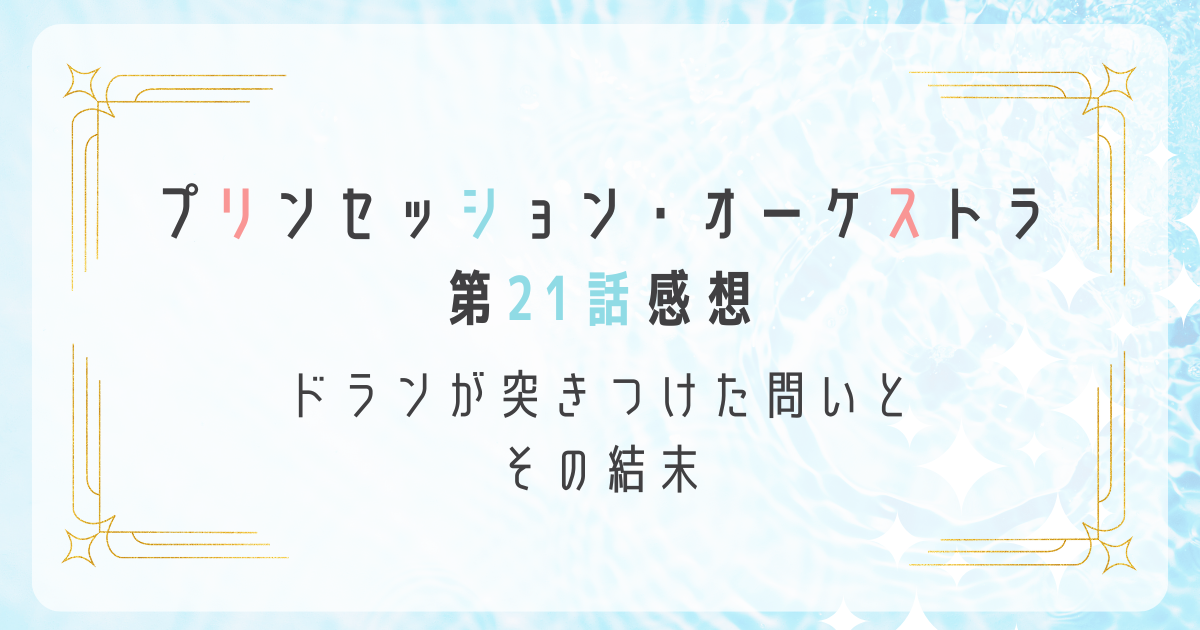
コメント