プリフェスの開幕、風花姉妹の合流、そして特殊ED。
あらすじだけを見れば、第39話は『プリンセッション・オーケストラ』がひとつの到達点に辿り着いた回のように見えます。
けれど実際に視聴後に残ったのは高揚感よりも、「これでよかったのだろうか」という引っ掛かりでした。
本来なら葛藤や選択の重みが響くはずの場面で、物語はあまりにもあっさりと答えを提示してしまったように思えます。
本記事では、プリオケ第39話が「始まりの回」ではなく、「問いを閉じてしまった回」に見えてしまった理由を掘り下げていきます。
風花姉妹は「答え」を持って来たのか?
Aパートで描かれたのは、風花姉妹となっちによる対話の場面でした。
そこでりりは、
みんなと歌いたいって。でも――私たち、そんなことをしてもいいんでしょうか? 許されてもいいんでしょうか?
引用元:『プリンセッション・オーケストラ』第39話
と、自分たちの立ち位置を確認するように問いかけます。
38話ですでに揺らいでいたこの感情が、39話ではよりはっきりと言葉として表に出た形です。
それに対して、なっちは迷いなく言葉を返します。
確かにさ、花の騎士のふたりは、みんなから笑顔を奪うようなことをしたんだよね。でもプリンセスのふたりはこれから、それ以上にみんなの笑顔を守れると思うんだ
引用元:『プリンセッション・オーケストラ』第39話
その返答は優しく、視聴者にとっても分かりやすい「正解」として提示されています。
しかし、ここでひとつ引っかかる点があります。
風花姉妹は、本当に「答えを探していた」立場だったのでしょうか。
「迷っているキャラ」として配置された違和感
このシーンでは、風花姉妹は「迷っている側」、なっちは「答えを与える側」として、明確に役割分担されています。
ですが、それはこれまで描かれてきた風花姉妹の姿と、微妙に噛み合っていません。
風花姉妹は、少なくとも白の女王のもとを離れて以降、自分たちの行動については一貫して「自分で考え、自分で引き受ける」姿勢を見せてきたキャラクターでした。
自分たちが許されないことをしたという自覚を持ち、その上で他者との距離をどう保つか、どこまで関わるべきかを、常にふたりで判断してきたのです。
だからこそ、36話・37話で描かれていた「距離を取る」という選択には、彼女たちなりの覚悟と筋が通っているように見えました。
その流れを踏まえると、第39話でりりが口にした「許されてもいいんでしょうか?」という言葉は、どうしても異質に響きます。
それは、これまで彼女たちが向き合ってきたはずの問い――「自分たちはどうするのか」「何を背負って生きるのか」――とは、少し別の方向を向いているように感じられるからです。
「納得させてもらう」物語への転換
本来、風花姉妹の物語は「自分たちで答えを出す」過程に価値がありました。
しかし39話では、その過程が描かれていません。
迷いが提示され、すぐに肯定が返り、場面は前へと進んでいきます。
結果として風花姉妹は、「答えを見つけた存在」ではなく、「答えを教えてもらい、納得した存在」として処理されてしまいました。
このズレこそが、39話を見たときに生じる最大の違和感です。
風花姉妹は本当に「迷っていた」のでしょうか。
それとも、物語の都合上「納得させてもらう役」に置かれただけなのでしょうか。
「自分で自分を許せない」は、いつ別の意味にすり替わったのか
第1章で見たように、風花姉妹は本来、他者の評価や感情とは切り離したところで、自分たちの行動を引き受けようとしていたキャラクターでした。
「許されないことをした」という認識は、誰かに裁かれたいという欲求ではなく、あくまで自分たち自身の中で完結していたはずです。
彼女たちが選んだ「距離を取る」「ふたりだけで戦う」という行動も、自己犠牲による贖罪というより、責任の所在を曖昧にしないための判断でした。
そこには「許されたい」よりも、「これは自分たちの問題だ」という線引きが強く感じられていました。
浮上した「許されたい」という別の問い
ところが38話、そして39話で繰り返される「許してもらってもいいのか」という言葉によって、前提が書き換えられていきます。
ここで描かれているのは、自分で自分を許せない苦しさではなく、「誰かに許してもらえたら前に進めるのではないか」という期待です。
問いの矛先が、自分自身から他者へと移動してしまっているのです。
その変化が「成長」として描かれていない問題
問題なのは、この変化が成長や心境の変化として丁寧に描かれていない点にあります。
なぜ他者の言葉が必要になったのか、何が彼女たちの中で揺らいだのか、その過程がほとんど示されていません。
結果として、「許される/許されない」という構図だけが前面に出てきてしまい、風花姉妹が自分で下していたはずの判断が、いつの間にか外部に委ねられてしまいました。
贖罪ではなく、「免罪」の物語になってしまった
その結果、風花姉妹の行動原理は、「自分で引き受ける責任」から「他者から与えられる免罪」へと意味合いを変えてしまったように見えます。
39話までの流れで描かれているのは、誰かが責任を果たした末に前へ進む物語ではありません。
「許されたことにして、次へ進む」ための構造です。
ここで明確にしておきたいのは、39話が「贖罪の物語」ではなく、「免罪の物語」になってしまった
という点でしょう。
なっちは「支える人」から「意味を与える人」になった
なっちはこれまで、風花姉妹のそばに立ち、感情を受け止める「支える人」として描かれてきました。
しかし第39話では、その役割が一段階変質し、彼女自身が物語の意味を言語化する存在へと押し出されています。
この変化は優しさの延長に見えながら、同時に物語の重心を大きく動かしてしまいました。
ケアを担ってきた存在としてのなっち
まず前提として、なっちがこれまで風花姉妹を気にかけ、支え続けてきたこと自体は否定されるものではありません。
水族館デートの場面でも、イベント準備の裏側でも、彼女は一貫して姉妹のそばに立ち、無理に踏み込まず、話を聞こうとしていました。
非戦闘員であるからこそ、物語の中で「気持ちに寄り添う役割」を担ってきた存在であることは確かです。
少なくともそこまでは、なっちは「支える人」として機能していました。
39話で変わってしまった立ち位置
しかし39話のBパート冒頭で描かれた対話において、なっちの立ち位置は明確に変わってしまいます。
りりの「許されてもいいんでしょうか」という問いに対して返されたのは、寄り添いや問い返しではなく、結論を伴う断定でした。
確かにさ、花の騎士のふたりは、みんなから笑顔を奪うようなことをしたんだよね。でもプリンセスのふたりはこれから、それ以上にみんなの笑顔を守れると思うんだ
引用元:『プリンセッション・オーケストラ』第39話
この言葉は優しく、前向きで、いかにも「正しい答え」に聞こえます。
ですが同時に、それは風花姉妹自身が辿り着くはずだった意味を、先回りして与えてしまう言葉でもありました。
「意味を与える言葉」が持つ強さと危うさ
なっちの言葉が力を持つのは、彼女が当事者ではない立場から、結論を示してしまったからです。
傷つけた側であり、その責任をどう引き受けるかを考え続けてきたのは風花姉妹自身であり、なっちは本来、その選択を見守る位置にいたはずでした。
それにもかかわらず、「これからは笑顔を守れる存在だ」という意味付けがなっちの口から語られたことで、風花姉妹は自分たちの葛藤を「自分の言葉で確定する側」から、「他人に説明される側」へと押し出されてしまいます。
それは支援というよりも、評価であり、承認を与える行為でした。
応援が「正解の配布」になってしまうとき
本来、応援とは相手の選択を後押しする行為です。
どの道を選ぶか、その意味をどう受け止めるかは、あくまで本人に委ねられるべきでした。
しかし39話のなっちは、風花姉妹の行動に対して「それは正しい」「意味がある」と結論づけてしまいます。
応援が、いつの間にか正解を配る行為へと変質してしまった瞬間でした。
4クール目で顕著になった「なっちへの機能集中」
この構造は、39話だけの問題ではありません。
4クール目に入って以降、ケア、調整、意味付けといった役割が、ほぼすべてなっち独りに集約されています。
その結果、ほかのキャラクターは「待つ」「受け入れる」「肯定する」側に固定され、問いや葛藤を引き受ける主体から外れてしまいました。
なっちが優しければ優しいほど、物語全体が単線的になっていく――
そんな歪さが、ここではっきりと表面化したように思えます。
動かないライブが象徴してしまったもの
第39話のラストは、プリンセス5人がステージに立ち、なっちの作った曲を歌うという、物語上は特別な場面でした。
特殊EDという形式からも、このライブがひとつの区切りとして描かれていることは明らかです。
しかし実際のライブ描写は、動きの少ない省エネなものに留まり、強い印象を残すには至りませんでした。
もちろん、これは単純に作画リソースの問題として片づけることもできます。
けれど、それだけでは説明しきれない軽さが、このシーンにはあったように思います。
問題は、この歌が誰にとっても「選択」や「賭け」になっていなかったことです。
風花姉妹にとっては、なっちの言葉によってすでに意味づけが済んでおり、歌うことは迷いの先にある決断ではなく、用意された結論になっていました。
みなもたちにとっても、このライブは何かを引き受ける行為というより、物語の流れに沿った結果として配置されていたように見えます。
そのため、このステージには緊張感が生まれません。
誰かが何かを失うかもしれない、あるいは踏み出すことで何かが変わるかもしれない、そうした賭けの感覚が描かれていないからです。
動かないライブは、そのまま動かない物語を象徴してしまいました。
もしこの場が、「それでも歌う」と誰かが決断する瞬間として描かれていたなら、たとえ動きが少なくても、印象はまったく違ったはずです。
第39話のライブは、物語の山場でありながら、同時にその限界を静かに示す場面にもなっていました。
まとめ|第39話は「始まり」ではなく「幕引き」に見えてしまった
第39話は、物語としてはひとつの到達点を描いた回でした。
風花姉妹は答えを持って現れ、プリンセス5人によるセッションは実現し、プリフェスは成功します。
表面的には、すべてが「うまくいった」回だったと言えるでしょう。
しかし、その過程で描かれたやり取りを振り返ると、いくつかの問いが置き去りにされたままにも感じられます。
「許されてもいいのか」という迷いは誰のものだったのか。
その答えは、本人たちが選び取ったものだったのか、それとも外側から与えられた意味だったのか。
なっちの言葉は支えであると同時に、行動の解釈をひとつに固定してしまう力も持っていました。
また、物語のクライマックスであるはずのライブシーンが、強い決断や賭けとして描かれなかったことも印象に残りました。
歌うことが「選ぶ行為」ではなく、すでに整えられた結論として配置された結果、物語はいつの間にか「ぬるま湯」のような手触りになっていたとも言えます。
第39話は、答えを提示した回であると同時に、問いを閉じてしまった回でもありました。
それが安堵として受け取れるか、物足りなさとして残るかは、視聴者それぞれの感じ方に委ねられています。
少なくとも本作はこの回で、「何を描き、何を描かないか」という選択をはっきりと示したのだと思います。
動画配信サイトのトライアル期間を使ってプリオケを視聴する方法と、解約時の注意点を別記事でまとめています。
- トライアル期間内に解約すれば課金されない
- 解約手順も事前に確認可能
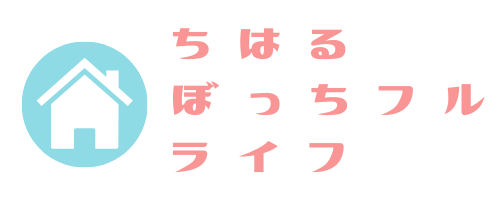

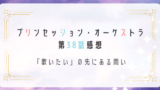
コメント