プリオケ第37話は、水族館デートという軽やかなエピソードでありつつも、前話で提示された問題がほとんど前に進まなかった回でもありました。
風花姉妹との距離は縮まったように見えて、根本的な立場のズレはそのままです。
むしろ36話で示された「責任」や「向き合い方」という問いが、同じ構図のまま繰り返されている印象すら受けました。
その中で浮かび上がったのは、主人公たちの「応援」が本当に他者に届いているのか、という疑問です。
本記事では、プリオケ第37話がなぜ前進ではなく足踏みに見えたのかを整理していきます。
- Princess Side
- Enemy side
第37話は「問いを進めなかった回」だった
第37話は、物語としてはあらすじどおりに進行するものの、36話で提示された問いに対して新たな答えや視点を提示する回ではありませんでした。
水族館デートというイベントを通じてキャラクター同士の距離が描かれる一方で、物語の核心にあったはずの問題は、ほとんど前進していないように感じられます。
この回は「何が描かれたか」よりも、「何が描かれなかったか」が強く印象に残る構成でした。
あらすじ通りに進む、進展のない展開
第37話は、水族館デートの企画と実行という、分かりやすく親しみやすいイベントを軸に進みます。
キャラクター同士が楽しそうに過ごす様子は丁寧に描かれており、単話として見れば決して出来が悪いわけではありません。
しかし、風花姉妹との関係性に注目すると、「距離が縮まったようで、実は縮まっていない」という印象が拭えません。
会話や行動に変化はあるものの、彼女たちが抱えている問題や葛藤そのものに踏み込む場面はなく、物語上の立ち位置は36話からほぼ変わらないままです。
結果として、この回は出来事は起きているのに、関係性の意味が更新されない展開になっています。
明確に進んだのは、りりとなっちの関係だけ
その中で、はっきりと前進したと言えるのは、りりとなっちの関係性です。
ふたりの間には、心の距離が縮まったことが分かる描写が明確に用意されていました。
この変化自体は自然で、キャラクターの感情の流れとしても納得できます。
しかし、それ以外の関係性はどうでしょうか?
物語の焦点であるはずの風花姉妹とみなもたちの関係については、表面的な交流が描かれるに留まり、根本的な問題には触れられていません。
誰と誰の関係が進んだのかがはっきりしている分、進まなかった関係性がより目立つ構成になっています。
36話の問題構図をなぞり直し、元の場所へ戻るだけの構成
第37話で描かれている関係性の構図は、基本的に36話から一歩も動いていません。
「私たちはもう気にしていない」とするみなもたちと、「自分たちに責任がある」と引き受けようとする風花姉妹という立場のズレは、そのまま据え置かれています。
水族館デートという非日常のイベントは、このズレを一時的に曖昧にし、問題を和らげようとする装置として機能していました。
しかしその時間は、風花姉妹がジャマスナークの出現を感知したことで中断され、物語は否応なく「戦い」と「責任」の現実へと引き戻されます。
みなもたちは後を追って加勢しようとするものの、実際に戦い、勝利を収めるのは風花姉妹だけです。
この展開によって、彼女たちが依然として「自分たちで片を付ける側」に立ち続けていること、そしてみなもたちがそこに踏み込めていないことを、あらためて強調します。
その直後に、かがりが「まだ私たちを受け入れてくれないんですか?」という問いを投げます。
それに対し、「この状況を招いたのは、白の女王に加担した私たちです」という、すみれの覚悟の言葉が続くことで、36話で提示された問題は解消されることなく、同じ形で再提示されることになります。
第37話は、新しい答えを示す回ではなく、36話の問題構図をなぞり直し、同じ地点に立ち戻ることを確認する回だったと言えるでしょう。
第37話が決定的に信頼を削った瞬間
第37話で感じた違和感や失望は、物語全体の停滞そのものというよりも、ある一点に集約されていました。
それは、36話で提示された「責任」や「覚悟」という重い問いに対して、物語がどう応答したのか、という点です。
すみれの覚悟を受け止める場面だったはずの会話
戦闘後、すみれは次のように語ります。
この状況を招いたのは、白の女王に加担した私たちです。だから、その責任を負って、ふたりだけで解決しないとならないんです
引用元:『プリンセッション・オーケストラ』第37話
この台詞は、風花姉妹が自分たちの過去と向き合い、責任を引き受けようとする姿勢をはっきりと言語化したものです。
36話から続く流れの中で見れば、ここは本来、彼女たちの覚悟をどう受け止めるのかが問われる重要な場面だったはずです。
受け入れるのか、否定するのか、あるいは別の道を提示するのか。
いずれにしても、すみれの言葉には真剣に向き合う必要がありました。
ながせの台詞がすべてを断ち切ってしまった
しかし、その直後にながせが放ったのが、次の一言です。
あーもう!責任責任って、一体誰が何を責めてるってんですかあ!
引用元:『プリンセッション・オーケストラ』第37話
この台詞が出た瞬間、第37話はそれまで積み重ねてきた問いを、自ら切り捨ててしまったように見えました。
なぜならこの言葉は、すみれの覚悟に寄り添うものでも、対話を試みるものでもなく、「その問い自体が無意味だ」と一方的に遮断するものだからです。
しかもこの台詞は、36話でなっちが示した「こっちがどう思ってるかじゃなくて、向こうが自分で自分を許せない」を完全に無視しています。
これまでの流れを踏まえるほど、「この言葉はどこから来たのか?」という疑問が強く残ります。
善意の押し付けが「正解」として描かれてしまった違和感
問題なのは、ながせのこの態度が、物語の中で批判されることなく、そのまま正解のように扱われている点です。
相手の心情や覚悟を受け止める前に、「そんなこと気にしなくていい」と切り捨てる。
そして、期待した反応が返ってこないことに苛立ちを見せる。
この構図は、「応援」や「寄り添い」とは真逆のものです。
にもかかわらず、第37話ではこの独善的な振る舞いが問題視されることなく、物語は次へ進んでしまいます。
36話でようやく浮かび上がったはずの問い――
「誰が、何を、どう引き受けるのか」というテーマは、ここで正面から向き合われることなく、押し流されてしまいました。
第37話が決定的に信頼を削った瞬間とは、まさにこの台詞が、問いを「終わらせてしまった」その一点にあったと言えるでしょう。
「応援」を掲げた主人公像は、どこで破綻したのか
プリンセッション・オーケストラは、公式設定や序盤の描写を見る限り、主人公・みなもを「応援する側」の人物として描いてきました。
しかし第36話・第37話を通して浮かび上がるのは、その「応援」が物語の中でうまく機能していないという違和感です。
ここでは、みなもたちの応援がどこでズレ始め、なぜ風花姉妹の問題と噛み合わなくなったのかを整理してみます。
みなもは本来「応援する側」のキャラクターだった
まず確認しておきたいのは、「応援」という要素が後付けではなく、最初から主人公像に組み込まれていた点です。
公式サイトのキャラクター紹介には、みなもについて「がんばる人が好きで、見ると応援したくなる」と明記されていますし、序盤では推し活に近い形ではあるものの、誰かを見守り、声援を送る姿が繰り返し描かれてきました。
また18話では、カリストがみなもの「応援する力」を高く評価する場面もあります。
この時点では、みなもの応援は単なる性格付けではなく、物語上の能力や資質として扱われていたはずです。
つまり、「応援」はプリオケ全体のテーマかどうかはともかく、みなもという主人公を理解するうえでは重要な軸だったと言えるでしょう。
かつては成立していた「応援」の成功体験
さらに重要なのは、みなもたちが「応援する側」として、きちんと機能していた回が存在することです。
16話ではながせが、17話ではかがりが、それぞれ悩みを抱えるクラスメイトの心情を受け止めた上で、背中を押しています。
このときの応援は、相手の状況や迷いを理解しようとする姿勢が明確に描かれていました。
「どうして悩んでいるのか」「何を怖れているのか」を共有したうえで、前に進む選択を尊重する。
本来の応援とは、まさにこうしたプロセスを含む行為だったはずです。
だからこそ、36話・37話で描かれるみなもたちの振る舞いは、成長がリセットされたかのようにも見えます。
あるいは、この成功体験が「応援すれば何とかなる」という思い込みを生み、相手の事情を深く掘り下げなくなってしまったのかもしれません。
応援が「理解」ではなく「押し付け」に変わった瞬間
36話・37話で顕著なのは、「私たちは気にしていない」「仲良くなりたい」という気持ちが先行しすぎている点です。
風花姉妹が何に責任を感じ、何を背負おうとしているのかを理解する前に、「気にしなくていい」「もっと馬鹿になっていい」と言ってしまう。
そこには、相手の感情に寄り添おうとする姿勢よりも、自分たちの善意を信じ切っている態度が目立ちます。
さらに問題なのは、その善意が受け入れられなかったとき、苛立ちとして表に出てしまうことです。
期待した反応が返ってこないことへの不満は、応援する側の都合でしかありません。
この時点で応援は、相手を支える行為ではなく、「こうあってほしい」という願望の押し付けに変質しています。
本来、応援とは相手の状況や感情を受け止め、その上で背中を押す行為です。
相手が何を背負い、何に迷っているのかを理解しようとする姿勢がなければ、応援は成立しません。
その前提を欠いたまま掲げられる「応援」は、善意であればあるほど独善的に響いてしまうのです。
なっちひとりに集約された「寄り添い」の役割
実際に風花姉妹へのフォローやケアを担っていたのは、みなもたちではなく、なっちひとりでした。
水族館デートの最中も、姉妹のそばにいて様子を気にかけていたのはなっちだけで、みなもたちは終始イベントを楽しむ側に回っています。
りりが「やっぱり(素の自分を見せるのは)怖いです」と本音を漏らした場面でも、その感情を否定することなく受け止め、さらに「いつまでも待ってるよ」とみなもたちの姿勢まで代弁していたのはなっちでした。
ここで描かれているのは、寄り添いや理解といった行為が、主人公側ではなく非戦闘員のなっちに集中している構造です。
みなもたちは「待つ」「受け入れる」というスタンスを取っているつもりであるものの、行動は「踏み込む側」のままで、その実践や感情労働を他者に委ねてしまっているようにも見えます。
その結果、みなもの行動原理として提示されてきたはずの姿勢が、物語の中で具体的なかたちを持たないまま宙に浮いてしまっているのです。
この構造を目にしたとき、「応援」とは一体誰の、どの行為を指していたのか、疑問を抱かずにはいられませんでした。
まとめ|問いを先送りにしたまま終わった、37話という回
第37話は、出来事としては穏やかで、決して荒れた回ではありませんでした。
水族館デートという日常的で楽しい時間が描かれ、キャラクター同士の距離が一部では確かに縮まっています。
ただその一方で、36話で提示された「罪や責任をどう受け止めるのか」という問題は、この回ではほとんど前に進きませんでした。
楽しい時間によって一時曖昧にされた問いは、戦闘をきっかけに再浮上し、結局は同じ構図のまま置き去りにされます。
印象的なのは、問題そのものが解消されなかったこと以上に、立場の違いに向き合おうとする姿勢が噛み合わないまま物語が終わった点です。
受け止めようとする側と、「気にしていない」と言う側。そのズレは修正されず、言葉だけがすれ違ったまま残されました。
この回は、何かを解決する話数ではありません。
むしろ、「向き合うべき問いが、まだ共有されていない」という事実を、はっきりと示した回だったように思えます。
だからこそ37話は、納得よりも違和感を残します。
その違和感を、物語が今後どう扱うのか――それを見極める段階に入った、そう感じさせる締めくくりでした。
動画配信サイトのトライアル期間を使ってプリオケを全話無料視聴する方法と、解約時の注意点を別記事でまとめています。
- トライアル期間内に解約すれば課金されない
- 解約手順も事前に確認可能
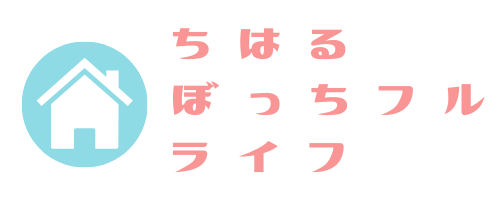
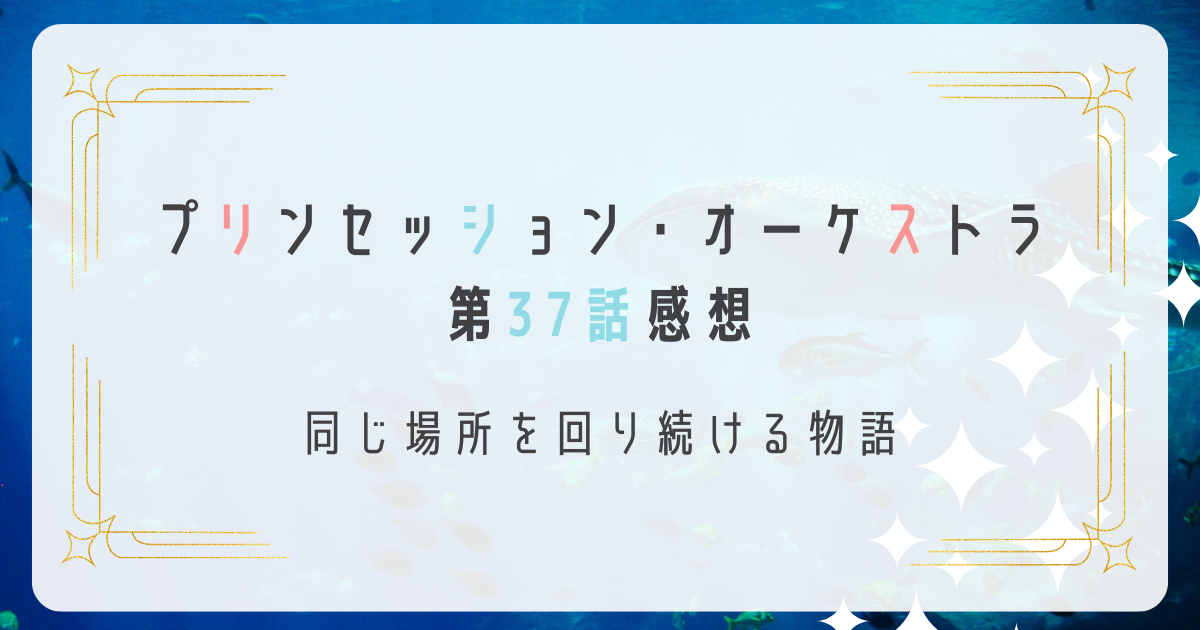
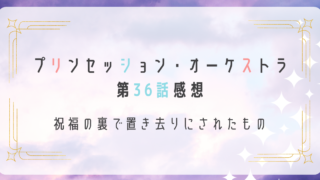

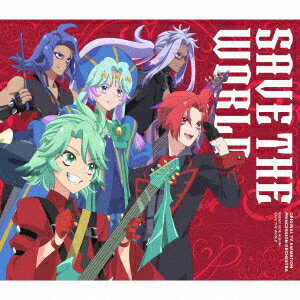

コメント