プリオケ第29話「二輪花」は、すみれ=シンシアの正体が明かされた余韻を引き継ぎ、風花姉妹とリップルの迷いを描く回でした。
アリスピアを愛するみなもに対し、「その『楽しい』の先にあるものを知らないで」と切り捨てるりり。
ふたりの視線の交差は、アリスピアという世界の「幸福の仕組み」に潜む痛みを静かにあぶり出します。
同じ「守りたい」という言葉でも、信じる者と疑う者では見える景色がまったく違う。
第29話は、プリンセスたちの理想の綻びと、風花姉妹の「もうひとつの正義」を予感させる転換点となりました。
動画配信サイトのトライアル期間を使ってプリオケを全話無料視聴する方法と、解約時の注意点を別記事でまとめています。
- トライアル期間内に解約すれば課金されない
- 解約手順も事前に確認可能
みなもの「応援の倫理」|支えたい気持ちがつくる距離
みなもの行動原理は、いつも「頑張る誰かを応援したい」というまっすぐな気持ちにあります。
それは特定の理念や信仰ではなく、彼女自身の性格に根ざした「優しさの衝動」です。
アリスピアを特別視しているのも、そこに「頑張っている女の子たちの笑顔」があるためです。
第29話でリップルがシンシアに対して「どうしてなんですか!」と叫んだのは、すみれの変化を「理解すべき※出来事」ではなく「応援に値する人が裏切った悲しい事件」として受け止めているから。
※共感・肯定・納得ではない
つまりみなもにとって、すみれは「対話する他者」ではなく、「信じる対象」だったのです。
応援は温かく、誠実な行為です。
しかし「相手を信じる」ことが前提になるぶん、「相手の痛みを同じ目線で見つめる」契機を奪ってしまうことがある。
この無自覚な立場の差こそが、みなもの「応援の倫理」の限界を示しています。
彼女の優しさは本物ですが、そこにはまだ問いかけの芽が育っていない。
その未成熟さこそが、みなもというキャラクターの魅力であり、同時に彼女の物語が今後どう成長するかを占う鍵でもあるのです。
りりの「問いの倫理」|「楽しい」の先にある痛み
りりの登場シーンは、みなもたちの明るい空気を切り裂くように挿入されます。
「(歌やダンスなど、みんなのいろんな「楽しい」に満ちているアリスピアのことが)あなたも好き?」というみなもの問いに、彼女ははっきりと「いいえ、全然」「嫌いです。歌もダンスも」と答えました。
この拒絶は単なる反抗ではなく、アリスピアという世界が抱える「もうひとつの現実」を突きつける行為です。
「楽しい」の裏にあるもの|見ないことで成立する幸福
みなもが「応援」や「楽しい」の側からアリスピアを見ているのに対し、りりはその明るさの裏にある痛みや犠牲を直視しています。
「その『楽しい』の先にあるのがどんなものなのかも知らないで」と続く台詞は、プリンセスたちが守ってきた「理想の世界」の表層性──すなわち、何かを見ないことで成立している幸福──を暴き出しているのです。
「嫌い」は拒絶ではなく、問い
りりの「嫌い」は、みなも個人への憎しみではなく、「知ろうとしないまま肯定すること」への拒絶。
それは、アリスピアの「楽しい」を盲目的に信じる構造への異議申し立てでもあります。
リップルが「支えたい」「守りたい」なら、りりは「この世界が本当にそれでいいのか」を問いただしたい存在です。
彼女の視線はアリスピアの仕組みそのもの──女の子たちの「楽しい」や「希望」が何によって支えられているのか──に向けられています。
信じる者と疑う者|交わらない「優しさ」
このふたりの対話が噛み合わないのは、リップルが「優しさ」の側から世界を信じ、りりが「真実」の側から世界を疑っているからです。
どちらも「どう生きるべきかという信念(righteousness)」を語っている。
だからこそ、彼女たちは互いを否定できず、理解もできない――そのすれ違いこそが第29話の核心なのです。
ピュリティという名の意味|欺瞞を許さない純度
リップルは「信じる者」として、りりは「疑う者」として、どちらも世界を一方向からしか見ていない。
それでも、りりの苛烈さはプリンセスたちに欠けていた視点──「光の裏にある痛みを見ようとする誠実さ」──を担っているように思えます。
彼女が「ピュリティ(純潔)」という名を持つのも象徴的です。
それは汚れていない純粋さではなく、むしろ欺瞞を許さない純度の高さ。
「楽しい」や「優しさ」に含まれる無自覚な支配や特権を見逃さない鋭さこそ、彼女の「問いの倫理」なのです。
風花姉妹の「二輪花」構造|同じ根を持つ、異なる咲き方
第29話のタイトル「二輪花」は、風花姉妹――すみれとりり――の関係性を象徴的に表しています。
ただし、それは「仲良し姉妹」といった単純な図式ではありません。
29話時点で描かれているのは、同じ信念を共有しながらも、温度や表現の仕方が異なるふたつの花の姿です。
穏やかなすみれ、苛烈なりり
すみれはアリスピアンを愛し、彼らの営みを「守ってあげたい」と語ってきました。
彼女は穏やかで、感情を抑えたまま理性的に行動するタイプです。
一方のりりは、言葉こそ少ないものの、その一言一言に苛烈な熱を感じさせます。
「嫌いです。歌もダンスも。その『楽しい』の先にあるのがどんなものなのかも知らないで」
この台詞は、プリンセスたちがアリスピアの「楽しさ」を無条件に肯定する姿勢に対する明確な異議として響きます。
りりが否定しているのは、アリスピアそのものではなく、そこに生きる少女たちの無邪気さ。
すみれが守ろうとしたアリスピアの「光」の部分を、りりは「影」として見つめています。
姉の恐れ、妹の覚悟
すみれはりりを戦場に出したくなかった――それは姉としての情にとどまらず、りりが抱く苛烈な正義が、「誰かを傷つける行為に変わってしまうのではないか」という恐れでもあったのかもしれません。
それでも、りりは戦場に立った。
姉が抑えてきた「痛み」や「怒り」を、彼女が代わりに表現するかのように。
二つの花が咲かせる「花の騎士」という存在
ふたりの姿は、理性と情熱、抑制と衝動というふたつのベクトルが同じ茎から伸びて咲いた花のようです。
プリンセス・ヴィオラとプリンセス・ネージュのジュエルベルが「ふたつの鍵を合わせてひとつになる」構造を持っているのも象徴的です。
彼女たちはどちらか一方では不完全であり、すみれの理性とりりの激情が揃って初めて、花の騎士という存在が成立するのかもしれません。
対話の回復とその限界|リップルと風花姉妹の交差点
第29話で印象的なのは、リップルがついに「敵」に対して声をかけたことです。
「どうしてなんですか! 風花先輩は自分の危険も顧みず女の子を助けていたのに!」
この台詞は、バンド・スナッチ編を通じて視聴者(というか私ね!)が抱えてきたフラストレーション――「なぜ主人公たちは、敵の事情を知ろうとしないのか」という問い――への、初めての応答でもありました。
成立しない「対話」|それでも生まれた「問い」
リップルの問いかけは、確かに対話とは呼べないものでした。
「どうしてなんですか! 風花先輩は自分の危険も顧みず女の子を助けていたのに!」という叫びは、理解よりも動揺と拒絶の感情が先に立っています。
シンシアの「あなたには分からない……!」に対して「そんなの当り前です! 言ってもらわないと分かるわけないじゃないですか!」と返す場面も、言葉が交わされながら噛み合わない――典型的な「対話のドッジボール」の構図です。
それでも、物語上は大きな変化がありました。
リップルは、初めて「敵を理解しようとする衝動」を外に向けたのです。※
これは拒絶の延長ではあっても、問いを発したという行為そのものが、これまでにない前進でした。
※18話のあらすじには「戦いではなく話をしようとする彼に、みなもは戸惑いつつも、理解をしようと努めます」とあるが、本編で「理解をしようと努めている」と解釈できるような能動的に対話を試みる描写はない。また、みなものカリストへの「問い」は糾弾である。
21話との対比|届かなかった問いと、届かないまでも放たれた問い
21話でも、かがりがドランに対して「アリスピアンだったのなら、どうしてこんなことを?」と問いを発しています。
しかしその「どうして」は、事実への驚きと拒絶から出た反射的な言葉にすぎず、相手を理解しようとする姿勢は感じられません。
ドランの「弱いやつが巻き込まれるのは知ったこっちゃあない」という答えも、対話を拒むものでした。※
それに対して29話のリップルの「どうして」は、感情的ではあっても、相手の行動の理由を知りたいという意志がかすかに見える。
結果的に会話は噛み合わず、対話にはなりませんでしたが、「敵を理解するための問い」として放たれたのは、これが初めてだったのです。
つまり、第29話は届かないままの問いを通して、プリンセス側にようやく「知ろうとする意志」が芽生えた回だったといえるでしょう。
※ドランが自分たちの出自を告白した時点で対話は決裂している。ドランの告白は第28話におけるすみれの「素顔」と同質のものである。
共感の線引きと、見えない「壁」
リップルは、愛らしいマスコットではなくなった異形のアリスピアンには共感できない。
けれど、すみれのように「自分と似た姿」をした者には共感の回路が開く。
この無意識の差こそが、プリンセスとアリスピアンを隔ててきた「壁」の正体です。
そして、風花姉妹はその壁を知っている。
りりが「楽しいの先にあるものを知らないで」と吐き捨てたのは、プリンセスたちが「痛みのある世界」を見ようとしない姿勢への批判であり、同時に、理解の線を引くリップルの無意識への痛烈なカウンターでもあるのではないでしょうか。
まとめ|断絶から対話へ──風花姉妹がもたらした「物語の転換点」
第29話「二輪花」は、プリンセスたちが掲げてきた「楽しい」という理想を、風花りりの登場によって問い直す回でした。
彼女の「その『楽しい』の先にあるのがどんなものなのかも知らないで」という言葉は、アリスピアの歪みを突く鋭い一撃です。
すみれとりりは、夢の国を守る側ではなく「夢の国の構造そのもの」を見据えている存在だと言えるでしょう。
プリンセスたちは今、初めて「理解できない他者」と向き合う段階に立たされました。
理想の維持から、理想の再定義へ──物語はここで、大きな転換点を迎えています。
動画配信サイトのトライアル期間を使ってプリオケを全話無料視聴する方法と、解約時の注意点を別記事でまとめています。
- トライアル期間内に解約すれば課金されない
- 解約手順も事前に確認可能
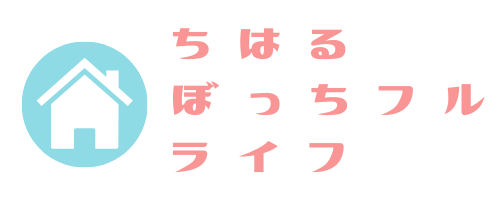

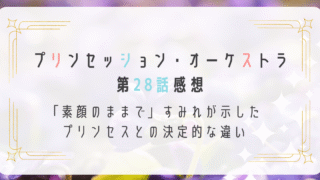

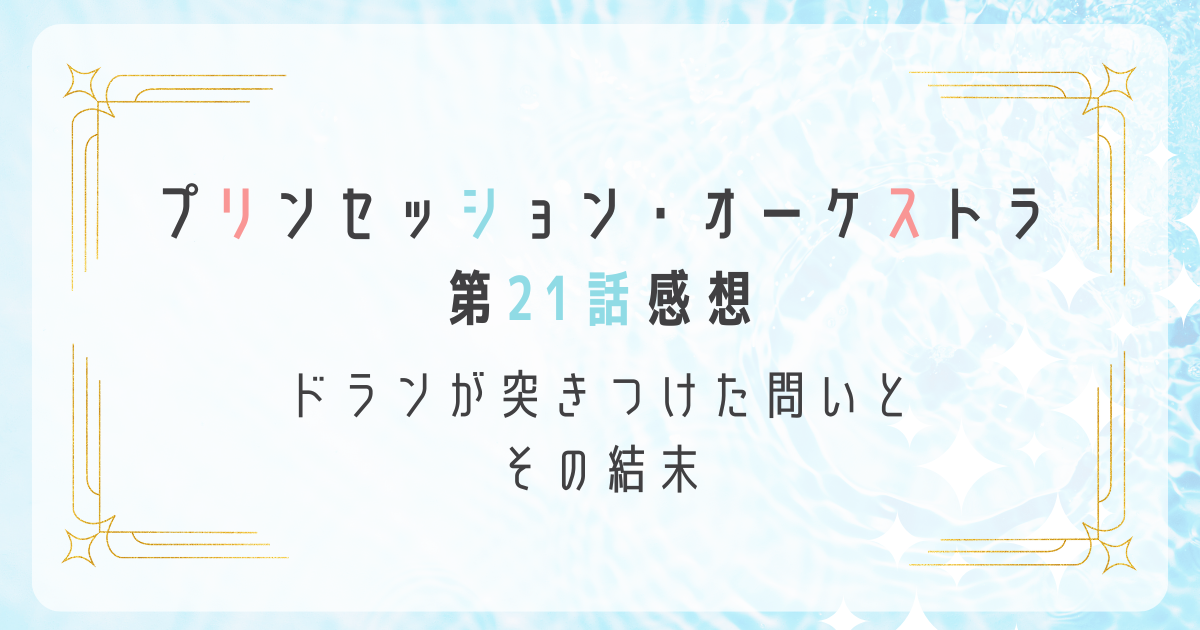
コメント