2024年10月20日公開
『チ。―地球の運動について―』は、15世紀のヨーロッパを舞台に、地動説を巡る人々の信念を描いた作品。
2024年10月5日からアニメの放送が開始されたことで、さらに注目を集めています。
私は原作でバデーニさんが嘔吐するシーンが好きなのですが、アニメのOPで毎回嘔吐してくれるので大変たすかります。
この記事では、作品の史実との関連を探り、さらに背景知識を深めるためのおすすめ書籍をご紹介。
ぶっちゃけおすすめしている書籍の中で実際に読んだのは1冊だけです。
実態は私が読みたい本リストです。申し訳ございません。
「父が子に語る科学の話 親子の対話から生まれた感動の科学入門」読了に伴い、該当箇所を更新しました。
- 原作
- ユリイカ 2023年1月号
- BD-BOX
『チ。―地球の運動について―』とは|アニメはどこで見られる?

| 著者 | 魚豊 |
| 出版社 | 小学館 |
| 掲載誌 | ビッグコミックスピリッツ |
| 連載期間 | 2020年9月14日~2022年4月18日 |
| 巻数 | 全8巻 |
| 話数 | 全62話 |
『チ。―地球の運動について―』は、地動説を題材に、中世ヨーロッパを舞台にした思想と学問の対立を描いた作品です。
科学と信仰、知識の伝承というテーマが、私たちに深い問いを投げかけます。
2024年10月5日からはアニメの放送がスタート。全25話の連続2クールで放送されました。
| 監督 | 清水健一 |
| シリーズ構成 | 入江信吾 |
| キャラクターデザイン | 筱雅律 |
| 音楽 | 牛尾憲輔 |
| 主題歌 | サカナクション『怪獣』 ヨルシカ『アポリア』 |
| キャスト | ラファウ:坂本真綾 ノヴァク:津田健次郎 フベルト:速水奨 オクジー:小西克幸 バデーニ:中村悠一 ヨレンタ:仁見紗綾 |
| アニメーション制作 | マッドハウス |
| 放送局 | NHK総合 |
| 放送期間 | 初回:2024年10月5日~2025年3月15日 再放送:2025年4月5日~ |
| 配信動画サービス | Netflix ABEMA |
| 公式サイト | https://anime-chi.jp/ |
| 話数 | サブタイトル |
|---|---|
| 第1話 | 『地動説』、とでも呼ぼうか |
| 第2話 | 今から、地球を動かす |
| 第3話 | 僕は、地動説を信じてます |
| 第4話 | この地球は、天国なんかよりも美しい |
| 第5話 | 私が死んでもこの世界は続く |
| 第6話 | 世界を、動かせ |
| 第7話 | 真理のためなら |
| 第8話 | イカロスにならねば |
| 第9話 | きっとそれが、何かを知るということだ |
| 第10話 | 『知』 |
| 第11話 | 『血』 |
| 第12話 | 俺は、地動説を信仰してる |
| 第13話 | 『自由』を |
| 第14話 | 今日のこの空は |
| 第15話 | 私の、番なのか? |
| 第16話 | 行動を開始する |
| 第17話 | この本で大稼ぎできる、かも |
| 第18話 | 情報を解放する |
| 第19話 | 迷いの中に倫理がある |
| 第20話 | 私は、地動説を愛している |
| 第21話 | 時代は変わる |
| 第22話 | 君らは歴史の登場人物じゃない |
| 第23話 | 同じ時代を作った仲間 |
| 第24話 | タウマゼインを |
| 第25話 | ? |
NHK総合にて毎週土曜23時45分から放送。
放送終了後に、Netflixで世界配信、ABEMAにて1週間無料配信されていました。
現在は、以下の動画配信サイトでも視聴可能です。
また、2025年4月5日からNHK Eテレにて2枠での再放送も決定しています。
- 4月5日(土)21時15分~
- 4月8日(火)24時00分~
アニメ版『チ。』は、作品の持つ重厚なテーマを見事に映し出すビジュアル演出が印象的です。
精緻な中世の街並みや、星空を見上げる人々の美しい姿が没入感を高めます。
さらに、サカナクションとヨルシカによる主題歌や、牛尾憲輔氏が手掛ける劇伴が物語を彩り、視聴者の心を揺さぶります。
『チ。―地球の運動について―』の史実との違いは?
- 史実では地動説支持者は弾圧されていない
- 実際に処刑された人間もいるが地動説だけが理由ではない
- 『チ。』は基本的にはフィクション。史実ではない
『チ。―地球の運動について―』は、地動説を巡る歴史的な背景を基にしながらも、フィクション要素を強く取り入れた作品です。
中心となる「地動説」は、コペルニクスが提唱し、のちにガリレオやケプラーが発展させた実在の理論。
しかし、登場人物やエピソードは多くが創作です。
特に、作中で描かれる「異端者の迫害」に関しても、史実との違いがあります。
史実がモデルになっている箇所については、後述の項目をご覧ください。
異端者迫害の描写と史実との違い
実際に、異端として迫害を受けた学者は存在しましたが、必ずしも地動説がその主な理由ではありません。
たとえば、ジョルダーノ・ブルーノは1600年に火刑に処されましたが、彼の場合、地動説以上に教会批判が問題視されたためです。
ジョルダーノ・ブルーノの異端嫌疑リスト
- 教会への政治的批判
- キリスト教の教義を否定
- 三位一体の否定
- 聖母マリアの処女性を否定
- 肉欲に耽溺
- 聖書を軽視
- 宇宙の多様性や無限性を支持(この辺に地動説を含む)
- 呪術などオカルトへの傾倒
- 輪廻説を信じ、人間の魂が動物にも移ると考えた
- 神を罵る
- 教皇を非難する
- 新たな教団を組織しようとした
など
また、ガリレオ・ガリレイは地動説を口実に異端審問にかけられましたが、命を落とすことはなく、最終的には軟禁の中で生涯を終えています。
フィクションとしての『チ。―地球の運動について―』
一方で、『チ。』の作中では、地動説そのものが異端として描かれ、登場人物たちが教会や権力から命を狙われます。
作品内での強烈な弾圧や迫害の描写は、史実とは異なる点が多く、作者もフィクションとしての意図を認めています。
それでもなお、『チ。』は、地動説を信じる者たちが命を懸けた情熱や、思想的葛藤を描き出している魅力的な作品には違いありません。
『チ。』は、物語の終盤にすべての根底を覆すと、急速に史実と整合しつつ、メタフィクション的な構造を形成します。
そして、物語の舞台は、15世紀のP王国から1468年のポーランド王国へと移行。
ラファウから始まった地動説に関する物語は、史実に繋がらない架空の世界として幕を閉じました。
しかし、「地球の運動」という概念は、伝書鳩によってフィクションから飛び出し、後にコペルニクスへと受け継がれることが示唆されます。
この作品に対して、「地動説支持者の迫害は史実ではない」という指摘や苦言が出ていますが、それを「読解力を持ち合わせていない愚者の痴れ言」と嘲笑するファンの声も少なくありません。
お互い相手を「史実とフィクションの区別がついていない奴」扱いしていて面白いですね。
しかし、そのような態度は必ずしも正当とは言えません。
『チ。』は、史実とフィクションの境界を曖昧にする要素が巧みに組み込まれています。
むしろ、史実とフィクションの区別を曖昧にしながら作者の掌の上で踊ることこそが、作品の本質を深く味わう方法なのではないでしょうか。
知らんけど。
地動説と天動説の基本|背景知識として知っておきたい天文学
『チ。』をフィクションとしてより深く楽しむためには、天文学の歴史を知っておくことが有益です。
特に、天動説と地動説の争いが宗教と科学の対立ではないことは、念頭に置いておくべきでしょう。
天動説の起源と影響
天動説(地球中心説)は、古代ギリシャのアリストテレスやプトレマイオスによって提唱された宇宙観です。
彼らは、地球の位置を宇宙の中心とし、天体が完璧な円軌道で地球の周りを回っていると信じていました。
これは宗教的にも調和の取れた秩序として、中世のキリスト教に受け入れられます。
教会はこの宇宙観を支持し、神の創造した秩序が反映されていると見なしていました。
天動説に基づく惑星運動モデルは非常に精度が高く、当時としては「科学的」であったことも重要です。
地動説とその革命的な意義
地動説は、紀元前3世紀にギリシャの天文学者アリスタルコスが最初に提唱しました。
彼は太陽を宇宙の中心とし、地球がその周りを回っているとする説を唱えましたが、当時はほとんど支持されませんでした。
のちに16世紀、ニコラウス・コペルニクスがこの説を発展させ、地球が太陽の周りを回るという理論を確立します。
しかし、コペルニクスの理論では惑星軌道が正円だったため、天動説よりも精度が低いものでした。
それでもなお「コペルニクス的転回」は、天文学だけでなく哲学的にも画期的なものであり、人間が宇宙の中心ではないという考え方を導入しました。
地動説は、のちにガリレオ・ガリレイやヨハネス・ケプラーによって科学的に証明され、ニュートンの万有引力の法則により完成します。
宗教と科学は対立していたのか
宗教と科学の対立は、単純に「科学が宗教と戦った」という二項対立では説明できません。
初期の地動説の提唱者であるコペルニクス自身がカトリックの聖職者であったことからも、宗教者全員が科学を否定していたわけではないことがわかります。
そもそも、教会がアリストテレスの天動説を採用したのは、教義の正当性を補強するための科学的な裏付けを欲したためです。
当時の知識体系において、天動説と地動説の対立は、科学と宗教の闘争ではなく、科学同士の対立だったと言ってよいでしょう。
また、コペルニクスを糾弾したのは、カトリックと対立していたルターであったことから、宗教対宗教という側面も見えてきます。
これらを踏まえると、『チ。』は、知と神という信仰の対立を描いた物語とも解釈できます。
『チ。』登場人物のモデルは誰?史実との共通点
ここまで散々「『チ。』はフィクションである」ことを強調してきました。
しかし、地動説が実在の理論である以上、史実や実在の人物がモデルとなっている箇所も存在します。
『チ。』と史実の共通点
たとえば、オクジーが満ちた金星を観測することで地動説を証明するくだり。
これは、ガリレオ・ガリレイが手製の天体望遠鏡で金星の満ち欠けを観測し、地動説を確信したエピソードがモデルでしょう。
また、ピャスト伯の膨大な観測データを元に、バデーニが惑星の軌道が楕円であることを導き出すという流れは、ヨハネス・ケプラーが「ケプラーの法則」を発見したエピソードが当てはまります。
ケプラーも、ティコ・ブラーエの観測データから惑星の軌道が楕円であることを解明しました。
『チ。』の登場人物のモデルは?
しかしながら、バデーニ自身はケプラーというよりは、ジョルダーノ・ブルーノに近い印象です。
ケプラーは偉い人(神聖ローマ帝国皇室付数学官)だったから、堂々と地動説を唱えても一切迫害されませんでしたし……。
ブルーノは修道士でしたが、知に貪欲なあまり古代哲学や異教の思想に手を出し、その結果異端の嫌疑をかけられ、国外逃亡。
十数年の放浪の末、ヴェネツィア貴族に招請されてイタリアに戻りますが、それがきっかけで、異端審問所に捕らえられてしまいました。
バデーニが亡命予定だったV共和国はヴェネツィア共和国を想起させて、意味深長です。
一方で、異端審問官のノヴァクには明確なモデルが存在します。
ナチスのアドルフ・アイヒマンを人物造形の参考にしたと、魚豊先生が公言しています。※
※出典:ぴあ音楽 『チ。』作者・魚豊が語る、“主観的な熱中”の尊さと危うさ 「気持ちに逆らえない人たちの姿を描きたい」
『チ。―地球の運動について―』がより楽しめる? おすすめ書籍6選
この項目では、読んでおくと『チ。』がより楽しめる(かもしれない)書籍をご紹介します。
比較的お手頃なものを選んだのですが、その結果、講談社の回し者みたいになってしまいました。
中でも『科学者はなぜ神を信じるのか』がおすすめ。
科学者でありカトリックの聖職者が書いたキリスト教の歴史+科学史の本で、『チ。』の副読本にぴったりです。
科学者はなぜ神を信じるのか コペルニクスからホーキングまで
『チ。』の作中で地動説に魅せられた人々の中には、修道士も存在します。
バデーニは教会の規律を無視して知を追い求めたために、右目を焼かれ田舎に左遷されてしまいました。
彼は教会よりも己の知識欲を優先する青年ですが、神への信仰心自体は捨てていません。
『科学者はなぜ神を信じるのか コペルニクスからホーキングまで』は、科学と宗教の関係を探る一冊。
本書では、歴史的に重要な科学者たちが、どのようにして「神」や「宇宙の創造者」との関係を見出してきたのかを解説しています。
科学者イコール無神論者として語られがちな一方で、実際には宇宙の神秘や秩序の背後に神の存在を感じていた点が強調されています。
著者の三田一郎氏は、物理学者にしてカトリックの聖職者です。
そのふたつの視点から、科学者がなぜ神を信じるのか、また神の概念がどのように科学の発展に影響を与えたのかについて丁寧に説明しています。
理系・文系問わず、科学や宗教に興味を持つ読者にとって、深い洞察を与えてくれます。
つまるところ、私たちが住むこの宇宙は、いまのところ地球上で知られている原子だけで構成されているのです。
したがって私は、宇宙全体を「地」と考えます。3000年前には、人間にはとうてい理解しがたい「天」と考えられていた領域が「地」となったのです。
引用元:三田一郎『科学者はなぜ神を信じるのか コペルニクスからホーキングまで(Kindle版)』(講談社 2018年6月 位置: 961)
人知の及ぶ範囲こそが地。
『チ。』を読んだ後だと感慨深い一文です。
父が子に語る科学の話 親子の対話から生まれた感動の科学入門
『チ。』に登場するピャスト伯は、生涯をかけて追求した天動説が間違いであったという事実に直面します。
彼の信念は揺らぎ苦悩しますが、最終的には、己の信念よりも「真理」を選びました。
そして、新しい発見を後世に繋げるために、自分の研究成果を若い世代に託します。
『父が子に語る科学の話 親子の対話から生まれた感動の科学入門』は、講談社ブルーバックスシリーズから刊行された科学入門書。
科学史家が8歳の息子と交わす対話を通して、科学の魅力と重要性を紹介する一冊です。
偉大な科学者たちの思考プロセスと、彼らがどのように間違えていたかに重点を置かれており、科学とは、連綿と受け継がれる試行錯誤と検証の営みであることが描かれています。
そうだ、かれらはまちがっていた。だがわれわれは終わりっこないと知りつつ、この大きな仕事をつづけている。なぜならわれわれは、お互いに助け合いながら科学を遂行できると考えているからだ。つまり、たとえ一人ひとりの人間があちこちで死んでいくとしても、われわれはこの科学という仕事を続けていくことができる。したがって、重要な問いは、そもそもなぜこの科学という仕事をするのかということになる。
引用元:ヨセフ・アガシ著 立花一希 訳『父が子に語る科学の話 親子の対話から生まれた感動の科学入門』(講談社 2024年7月 P26)
専門的な知識を持たない読者でも科学の世界に親しみやすく、科学の中核をなす相互吟味を体験できる構成となっています。
科学への興味を育む一冊として、科学に興味を持ち始めた中高生にもおすすめです。
キリスト教入門(講談社学術文庫)
『チ。』本編で、キリスト教(C教)自体にスポットライトが当たることはほとんどありません。
ですが、中世ヨーロッパを舞台にした物語をより深く読み解くなら、キリスト教についての知識を身に着けておいて損はないでしょう。
『キリスト教入門』(講談社学術文庫)は、キリスト教の基本的な教義や歴史的な展開を平易に解説した入門書です。
この本では、キリスト教の神学的な背景に加え、ヨーロッパ文化に大きな影響を与えた宗教としてのキリスト教がどのように発展してきたのかが詳しく説明されています。
特徴的なのは、著者がキリスト教の歴史を通じて神学的な議論にとどまらず、哲学、政治、芸術などさまざまな角度からキリスト教を分析している点です。
また、カトリック、プロテスタント、正教会といった各宗派の違いも理解しやすく整理されています。
初学者にも分かりやすく、キリスト教がなぜ歴史的に重要であるかを学ぶことができるため、宗教や文化に興味のある方には最適な一冊です。
試し読みで目次を読んで「なんだか難しそう……」と感じた方は、岩波ジュニア新書の『キリスト教入門』はいかがでしょうか。
天の科学史
こちらも科学史の本ではありますが、『科学者はなぜ神を信じるのか』『父が子に語る科学の話』と異なり、天文学に焦点を当てた一冊。
『天の科学史』は、天文学の歴史を通じて人類が宇宙とどう向き合ってきたかを探る書籍です。
星座の観測、占星術の誕生、暦の作成から、コペルニクスの地動説、現代の天体力学の発展まで、幅広く天文学の歴史を網羅しています。
さらに本書は、科学が宗教や権力、社会とどのように関わり、宇宙観がどのように変化してきたかに注目。
「天への恐れ」から始まった天体観測の起源を探り、科学と信仰の関係性に焦点を当てています。
原著は1984年に刊行されましたが、その内容は今なお色褪せることなく示唆に富んでいます。
中世ヨーロッパの社会観
中世ヨーロッパに生きた人々の社会観は、神学的宇宙観によって規定されていました。
『中世ヨーロッパの社会観』は、中世ヨーロッパにおける社会構造を、隠喩を通して解説した一冊です。
中世社会では、教皇と皇帝が統治する階層秩序が特徴的でした。
著者は、人体や建築物、蜜蜂、チェス盤といった具象的な隠喩を用いて、各社会階層の役割を説明。
特に身分制度がこの時代の社会像を強く反映しており、宗教と政治の融合が鮮明に描かれています。
本書は、複雑な中世社会を理解するための優れたガイドであり、具体例を挙げながら、階層的な社会秩序がどのように機能していたかを明快に解説しています。
中世ヨーロッパ:ファクトとフィクション
中世ヨーロッパに対する誤った認識は数多く存在します。たとえば、ガリレオ裁判は中世ではなく近世の出来事です。
『中世ヨーロッパ:ファクトとフィクション』は、中世ヨーロッパに関する誤解や伝説を、史実に基づいて丁寧に検証し、その真実と虚構を分けることをテーマにした本です。
この書籍は、広く知られている中世の誤った歴史観を紹介し、それがどのように形作られ、現代まで伝わってきたのかを解き明かしています。
各章では、中世にまつわる一般的な神話や誤認を取り上げ、それらを当時の史料を元に批判的に検討し、誤解の背景を分析。
この本は、中世ヨーロッパの実像を深く理解したい読者や、歴史に興味のある方々にとって、学びの宝庫となるでしょう。
邦訳されている地動説支持者の著作
地動説は、科学史における大きな転換点であり、近代天文学の礎を築いた重要な理論です。
この項目では、地動説を支持した歴史的な人物たちの著作を4冊ご紹介します。
この中で、お手頃な価格で新品が手に入るのは『天球回転論 付 レティクス「第一解説」』と、ガリレオの項で併せて紹介している『星界の報告』の2冊。
ほかの書籍は高額であったり絶版であったりと、やや入手ハードルが高くなっています。
コペルニクス|天球回転論 付 レティクス『第一解説』
『天球回転論』は、ニコラウス・コペルニクスが16世紀に発表した画期的な著作であり、天文学と科学史において非常に重要な位置を占めています。
コペルニクスは、それまでのプトレマイオスの地球中心の宇宙観に挑み、地動説を提唱することで、従来の天文学の枠組みを大きく変えました。
『天球回転論』全6巻のうち、本書には地球の運動について記された第1巻と、コペルニクスの弟子レティクスによる『第一解説』を付録。
コペルニクスの理論をさらに深く理解するための補足的な情報が提供されています。
この著作は、後にケプラーやガリレオ、ニュートンといった科学者に大きな影響を与え、「科学革命」の基礎を築きました。
なお、完訳版はみすず書房から出版されています。
ジョルダーノ・ブルーノ|無限・宇宙・諸世界について
※リンクをクリックするとAmazonへ移動します
『無限・宇宙・諸世界について』は、16世紀の哲学者ジョルダーノ・ブルーノが提唱した無限宇宙論を詳述した書籍です。
本書では、『聖灰日の晩餐』で取り上げられた「宇宙の無限性」というテーマをさらに深く掘り下げています。
彼は、宇宙が無限であり、無数の星々や惑星(「世界」)が存在すると主張しました。
これらの「世界」は固定されず、宇宙空間を自由に動く存在として描かれています。
ブルーノの思想は、当時の主流であったアリストテレスの天動説に真っ向から対抗し、近代天文学に影響を与えました。
『無限・宇宙・諸世界について』は、ブルーノの革新思想を理解するための重要な一冊です。
岩波文庫版もありますが、現在は絶版となっています。
ガリレオ・ガリレイ|天文対話
『天文対話』は、ガリレオ・ガリレイが1632年に発表した科学書です。
ガリレオは、対話形式で登場人物を通じて、様々な科学的議論を展開し、地球が宇宙の中心ではなく、太陽の周りを公転しているという考えを説きました。
この書籍は、彼の著作の中でも特に注目を集め、科学史上の大きな転換点とされています。
ガリレオは、観測や理論の両面から、天動説が抱える矛盾を明らかにし、実験的な方法論の重要性を強調。
木星の衛星の運動や、金星の満ち欠けなどの現象を挙げ、地動説がより現実に即していることを証明しようと試みました。
『チ。』で、オクジーが金星の満ち欠けを観測するエピソードは、ガリレオに由来していると推測します。
『天文対話』はその内容が大きな波紋を呼び、ガリレオはのちに異端としてローマ教会の裁判にかけられ、終身軟禁を命じられました。
この著作は、近代科学の幕開けを告げる一冊として、いまなお多くの読者に読み継がれています。
ケプラー|新天文学
『新天文学』は、天文学における画期的な業績を扱ったヨハネス・ケプラーの名著です。
本書は、ケプラーがティコ・ブラーエから受け取った膨大な火星の観測データをもとに、惑星の軌道が円ではなく楕円であることを解明したプロセスを詳細に描いています。
これにより、ケプラーの第1・第2法則が確立され、ニュートン力学の基礎が築かれました。
『チ。』に登場したピャスト伯のモデルは、おそらくティコ・ブラーエでしょう。
工作舎より出版されている『新天文学』は、ラテン語の原典を日本語で初めて完全に翻訳した貴重な一冊。
天文学者や科学史家にとって非常に価値の高い参考資料となっています。
まとめ
『チ。―地球の運動について』は、地動説を巡る人々の信念や葛藤を非常にドラマチックに描いており、「信念を貫くことの困難さ」や「真実を追求する意義」を強く伝えます。
しかし、作中の地動説に関する描写は、誇張されている点が多いことに留意が必要です。
たとえば、教会が地動説を厳しく弾圧する描写がありますが、実際には教会がコペルニクスに意見を求めるなど、必ずしも一方的に迫害されていたわけではありません。
アニメや原作漫画を楽しむ際には、フィクションとして楽しみつつも、当時の歴史的な背景にも興味を持ってみると、より深い理解が得られるかもしれません。
- 原作
- ユリイカ 2023年1月号
- BD-BOX
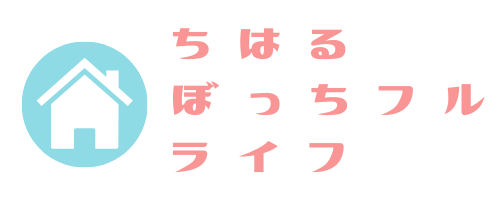
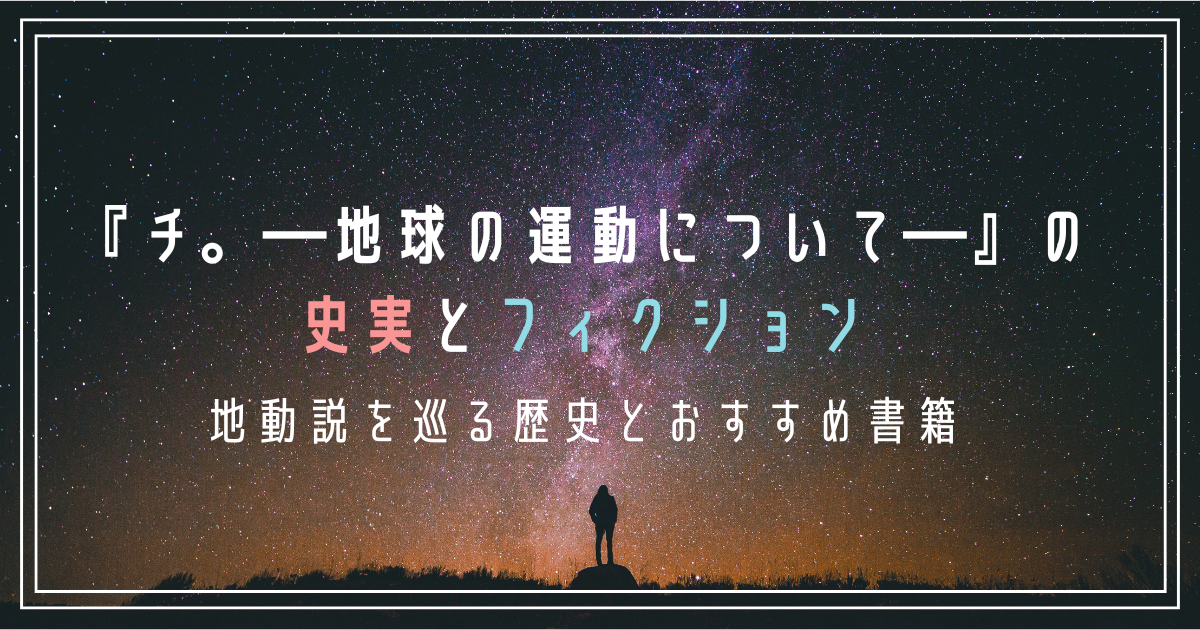
















コメント