プリオケ第36話は、風花姉妹のその後と白の女王の再始動を描いたエピソードでした。
一見すると物語は前に進んだように見えますが、視聴後に残るのは安堵よりも、拭いきれない違和感です。
それはキャラクターの好き嫌いではなく、誰が許し、誰が背負い、誰が語られなかったのかという構造的な問題に起因しています。
とくに本話では、「気にしなくていい」という善意が、かえって他者の罪や苦悩を押し流してしまう危うさが強く浮かび上がりました。
本記事では第36話を通して揺らいだ倫理、正義の置きどころ、そして物語が先送りにした問いについて掘り下げていきます。
「もっと馬鹿になってもいい」という言葉の危うさ
第36話で最も強い違和感を残したのは、善意や優しさの言葉が、かえって他者の罪悪感や内省を押し流してしまった点でした。
「許す」「気にしない」という態度は一見すると救いに見えますが、その立ち位置が誰のものであるのかを誤ると、倫理は簡単に揺らぎます。
この章では、その危うさが最も露わになった場面を掘り下げていきます。
なっちの言葉が示していた「正しい問題提起」
なっちが口にした
たぶんさ、こっちがどう思ってるかじゃなくて、向こうが自分で自分を許せないんじゃないかなあ
引用元:『プリンセッション・オーケストラ』第36話
という言葉は、第36話において数少ない地に足のついた視点でした。
風花姉妹が抱えているのは、他者から責められている苦しさではありません。
自分たちが何をしてきたのかを理解したうえで、それをどう受け止めればいいのか分からない、という内側の問題です。
罪悪感や責任感を抱くこと自体は、決して不健全なものではなく、むしろ真っ当な反応でしょう。
なっちはその点を、「許す/許さない」という外側の評価にすり替えることなく、「当人が自分自身をどう裁いているか」という核心に触れていました。
この問題意識自体は、風花姉妹を突き放すものでも、甘やかすものでもありません。
だからこそ、この時点ではまだ、物語は倫理的に踏みとどまっていたと言えます。
風花姉妹の苦悩を「厄介な空気」として処理せず、向き合う余地が残されていたからです。
ながせの台詞が覆してしまったもの
なっちの言葉が提示していた問題意識は、ながせの
真面目か! もっと馬鹿になってもいいと思うんですけど!?
引用元:『プリンセッション・オーケストラ』第36話
という一言で、あっさりと上書きされてしまいました。
この台詞が厄介なのは、表面上は明るく、前向きで、場の空気を和らげる言葉として機能している点です。
しかしその実態は、「私たちはもう気にしていない」という立場から、風花姉妹の葛藤を軽く扱う態度に他なりません。
罪悪感や責任感を抱くこと自体が、まるで「考えすぎ」「ノリが悪い」もののように処理されてしまっています。
さらに問題なのは、みなもたちが無自覚のうちに「許す側/許される側」という構図に立っていることです。
誰が、いつ、その権限を持ったのでしょうか。
少なくとも風花姉妹は、まだその土俵に立つことすら選んでいません。
この瞬間、物語は「どう向き合うか」という問いから逸れ、「気にしないと言っている側の善意」を優先する方向へと舵を切ってしまいました。
なっちの問題提起が示していた繊細な論点は、ここで事実上、封じられてしまったのです。
「素直に仲間にならなかった」風花姉妹は正しかったのか
第36話で描かれた風花姉妹の態度は、一見すると物語の足踏みにも見えます。
しかし同時に、それは「簡単に仲間になること」への違和感を、彼女たちなりに引き受けた結果でもありました。
この選択は評価できる点と、どうしても拭えない問題点の両方を含んでいます。
評価できる点|安易な和解を選ばなかったこと
まず評価したいのは、風花姉妹が祝福ムードに流されなかった点です。
プリンセス誕生を歓迎されながらも、彼女たちは自分たちの過去の行いを「なかったこと」にせず、距離を取る選択をしました。
これは、物語的にはかなり真っ当な反応です。
自分たちがやってきたことを思えば、笑顔で手を取ることができない──その感情はごく自然であり、むしろ誠実です。
少なくとも「仲間にならない=ひねくれている」「素直じゃない」と切り捨てられるような態度ではありません。
また、「独自にプリンセスとしてアリスピアを守る」と誓う姿勢も、逃避ではなく責任の取り方の一つとして読めます。
主人公側の輪に入る前に、自分たち自身の立場を定めようとするこの判断そのものは、十分に妥当だと言えるでしょう。
それでも拭えない「予定調和感」
一方で、風花姉妹の苦悩描写が、どこか「予定された通過点」に見えてしまうのも事実です。
悩んでいる、後悔している、距離を取っている──それらは確かに描かれていますが、それ以上踏み込んだ問いには触れられていません。
具体的には、「では、何をもって償いとするのか」「どんな痛みを引き受け続けるのか」という部分です。
禊や贖罪が言葉としても行動としても明示されないまま、関係性だけが少しずつ前に進んでいく構成は、どうしても弱く見えてしまいます。
結果として、苦悩そのものが「ちゃんと悩んでいますよ」「すぐ仲間にしませんでしたよ」というアリバイのように機能してしまっている印象を拭えません。
風花姉妹が抱えている重さは本来、もっと物語を軋ませる力を持っているはずです。
それが「予定された展開」として処理されてしまったとき、納得ではなく、割り切れなさだけが残ります。
みなもの言葉が示す「善良な傲慢さ」の再浮上
第36話で改めて浮かび上がったのは、風花姉妹の問題というよりも、みなもたち主人公側のスタンスでした。
それは悪意でも冷酷さでもありません。
むしろ善意に満ちているからこそ、余計に厄介な歪みです。
ここで顔を出したのは、これまで何度も描かれてきた「善良な傲慢さ」の再来でした。
「同じプリンセス」という雑な括り
みなもの「私たち、同じプリンセスなのに、こんなにも距離が遠い」という言葉は、一見すると歩み寄りの意思表明に見えます。
しかしこの台詞は、前提そのものが雑です。
主人公たちと風花姉妹では、背負ってきたものが決定的に違います。
何も知らない普通の少女としてプリンセスになった者たちと、女王に力を与えられ、人外の領域に足を踏み入れ、他者を傷つけてきた側。
その非対称性を無視して「同じプリンセス」という肩書きだけで距離を測ろうとすること自体が、すでにズレています。
距離が遠いのは当然です。
遠い原因は感情ではなく、立場と経験の差にあります。
そこをすっ飛ばして「同じなのに」と言ってしまう時点で、相手が抱えている重さを真正面から見ていないのです。
34話の反省はどこへ行ったのか
34話では、みなも自身が「自分たちの言動が風花姉妹を傷つけていた」という自覚に至っていました。
その描写によって、これまでの強引さや一方通行な善意は、意図的な演出だったのだと多くの視聴者は受け取ったはずです。少なくとも私はそうでした。
しかし36話で見えたのは、その反省が継続していない姿です。
「私たちは気にしていない」「同じプリンセスなのに」という言葉は、相手の痛みよりも、自分たちの納得を優先してしまっています。
ここで復活してしまったのは、善意であれば何を言っても許される。善意で差し出した手は、受け取られて当然という構造です。
それは優しさではなく、無自覚な支配に近い。
34話で芽生えたはずの自己批判が、物語の都合によって後退してしまったように見える点が、この章最大の違和感でした。
ヴィオラ&ネージュの戦闘が際立って見えた理由
第36話で強く印象に残ったのは、皮肉にも主人公チームではなく、ヴィオラ&ネージュの戦闘シーンでした。
それは「新キャラだから」「作画がよかったから」という単純な理由だけではありません。
35話・36話を通して積み重なってきた構造的な歪みが、この場面で一時的に解消されていたからです。
主人公チームが介入しないことの強さ
ヴィオラ&ネージュの戦闘が心地よく映った最大の理由は、主人公チームが介入しなかったことにあります。
そこには、余計な説得、感情のすり合わせ、倫理的な立ち位置の確認といった処理が入りませんでした。
歌が始まれば戦いが始まり、戦いが続いている間は、歌とアクションが物語の主役であり続ける。
女児向けバトルアニメとして、極めて素直で、極めて強い構成です。
35話のお披露目回ですでに感じられていたこの快感は、36話でさらに明確になりました。
誰かの価値観を是正しようとしない。
誰かの罪を軽くもしないし、裁こうともしない。
ただ「守るために戦う」という一点に集中できていたからこそ、戦闘そのものの完成度が際立ったのです。
35話・36話を通して見える構造的問題
ここで浮かび上がるのは、かなり皮肉な構図です。
主人公側が深く関われば関わるほど、物語の中で倫理・感情・正義が濁っていく。
一方で、ヴィオラ&ネージュのように距離を保った存在ほど、物語上の役割が明確になる。
主人公チームは「理解する側」「許す側」に立とうとするがゆえに、言葉が重くなり、判断が曖昧になります。
それに対してヴィオラ&ネージュは、今のところ誰かを裁く役割を背負っていません。
だからこそ、彼女たちは第三勢力として、純粋に「行動」で語ることができているのです。
この立ち位置は、物語全体のバランスを取るうえでは非常に重要です。
同時に、「主人公であること」が必ずしも物語上の強みになっていないという問題も、浮き彫りにしてしまいました。
戦闘がよかった、という感想の裏側には、余計なものが削ぎ落とされた瞬間だけ、この作品は一番輝くという、少し苦い評価が隠れているのかもしれません。
バンド・スナッチが「語られない」ことの決定的な問題
第36話までを通して、最も大きく置き去りにされている存在――それがバンド・スナッチです。
彼らは倒された敵であり、被害を生んだ存在であり、そして同時に、まだ終わっていない存在でもあります。
にもかかわらず、物語は彼らについて「語らない」選択を続けています。
完全消滅ではないが、作中では失われた存在
視聴者の視点から見れば、バンド・スナッチは完全消滅していません。
彼らはミューチカラとなって赤の女王のもとへ還り、その赤の女王もまた、歌のカケラを残して消滅しました。
歌のカケラは現在ナビーユが管理しており、順当に考えれば、その中にバンド・スナッチが眠っている可能性は十分にあります。
しかし、これはあくまで視聴者だけが知っている情報です。
作中の人物たちは、バンド・スナッチを「かつて倒した敵」としてしか認識していません。
この視点の断絶こそが、物語の語りに決定的な歪みを生んでいます。
キャラクターたちは、彼らの不在を前提に話を進め、罪や和解や前進について語る。
けれど視聴者は、「本当に終わったのか?」という疑問を抱えたまま、そのやり取りを見せられるのです。
「どうせ後で復活する」という扱いへの違和感
問題なのは、復活の可能性そのものではありません。
違和感の正体は、重要な犠牲や存在を語らないまま物語が進んでいくことです。
バンド・スナッチ――そしてカリストは、確かに言葉を残しました。
彼らなりの思想があり、葛藤があり、世界に対する視線がありました。
にもかかわらず、それらは十分に回収されないまま、物語の表舞台から降ろされています。
「どうせ後で復活するから」「今は触れなくていいから」そう言わんばかりの扱いは、物語の重みを確実に削いでいきます。
敵の言葉を回収しないという選択は、主人公側の正義や選択をも、結果的に軽くしてしまう。
語られなかったものは、なかったことにはならないからです。
公式二次創作としての「みにまんが」が生む違和感
バンド・スナッチのみにまんがは、本編の補足でも後日談でもありません。
物語上の因果や設定とは切り離された、いわば公式が出している二次創作に近い立ち位置のコンテンツです。
彼らがわちゃわちゃと日常的なやり取りをする、同人誌的な内容と言っていいでしょう。
それ自体は、単体で見れば楽しい試みです。
しかし問題は、本編においてバンド・スナッチがほとんど語られないまま退場している、という事実があることです。
物語の中では向き合うことを避けて切り捨てておきながら、ファン向けの場では可愛さや人気だけを抽出して供給する。
そうした態度が、キャラクターを都合よく使い分けているように感じられてしまうのです。
特に引っ掛かるのは、連載の扱いです。
2クール目の半ばから週1で12話分が連載され、きれいに終了したはずのみにまんがが、12月20日、何の前触れもなく13話を公開しました。
素直に喜びたい気持ちはあります。
しかし、本編でのバンド・スナッチの扱いがあまりに曖昧なままである以上、「ファンの不満を和らげるための供給ではないのか」という下種の勘繰りが生まれてしまいます。
本編で語るべきだった存在を、本編とは無関係な場所でだけ愛嬌たっぷりに描く。
それはガス抜きにはなっても、物語の問題解決にはならない。
むしろ、「なぜ本編では語らなかったのか」という疑問を、より強くしてしまうのです。
第36話は前進だったのか、それとも問題の先送りか
第36話は、物語が停滞しているわけではありません。
しかし動いたのは状況や立ち位置であって、これまで積み重ねられてきた倫理的な問いそのものではありませんでした。
前進しているように見えるからこそ、「何が解決されずに置き去りにされたのか」が、よりはっきり浮かび上がる回でもあります。
表面上は前に進んでいる
第36話は、状況だけを見れば確かに「動いた回」ではあります。
風花姉妹は安易に主人公側へ合流せず、第三の立ち位置を選びました。
これは、彼女たち自身が自分たちの行為を軽く扱っていないことの表明でもあり、一定の評価はできます。
また、白の女王も花の騎士を失ったまま沈黙するのではなく、ミューチカラの過剰を抑制するために再び動き始めました。
敵対構造そのものが再編されつつある、という意味では、物語は確かに前進しています。
少なくとも「何も起きなかった回」ではありません。
しかし、それはあくまで配置が変わっただけの話です。
しかし核心は何ひとつ解決していない
問題は、その配置変更が何の問いにも答えていない点にあります。
正義の線引きは曖昧なまま、誰が裁かれ、誰が裁かれないのかという基準も示されていません。
バンド・スナッチが救われなかった理由と、風花姉妹が祝福される理由の差は、いまだ言語化されないままです。
そして最も厄介なのは、その差を誰も引き受けていないことです。
主人公たちは「気にしていない」と言い、風花姉妹は自責の中に留まり、物語そのものは次の展開へ進んでいく。
結果として、「救われた者/救われなかった者」の非対称性だけが宙吊りにされ、問いそのものが先送りにされています。
第36話は前に進んだように見えて、実際には問題から一歩横にずれただけの回でした。
だからこそ、視聴後に残るのはカタルシスではなく、解消されない違和感なのだと思います。
まとめ|この物語は「誰向け」であるべきだったのか
『プリンセッション・オーケストラ』は、放送枠やビジュアル、販促の構造から見れば「女児向けアニメ」として設計されています。
そうであるなら、本来必要だったのは、誰が悪くて、なぜ戦うのか。そして何が許され、何が許されないのかという線引きを、子供にも理解できる形で提示する説明責任でした。
しかし本編はその責任を、視聴者の感情や空気読み、そして「察し」に委ねてしまったように見えます。
一方で「全人類向け」を標榜するなら、求められるのは別の覚悟です。
情や葛藤を描くなら、それによって生まれる矛盾や不公平、救われなかった存在の重さから目を逸らさず、物語として引き受ける必要がありました。
バンド・スナッチが語られず、正義の線引きが曖昧なまま進む構造は、その覚悟が最後まで定まらなかったことの表れでしょう。
この作品が描いてきたのは、確かに「情」の物語です。
しかし情は、正義の代替にはなりません。
情で人を救うこと自体が悪なのではなく、それを正義の顔をして振る舞わせてしまったとき、物語は最も危うくなります。
誰に向けた物語だったのか。
そして、誰に何を考えさせたかったのか。
第36話までを見届けた今、その問いそのものが、この作品に残された最大の宿題なのかもしれません。
動画配信サイトのトライアル期間を使って『プリンセッション・オーケストラ』を視聴する方法と、解約時の注意点を別記事でまとめています。
- トライアル期間内に解約すれば課金されない
- 解約手順も事前に確認可能
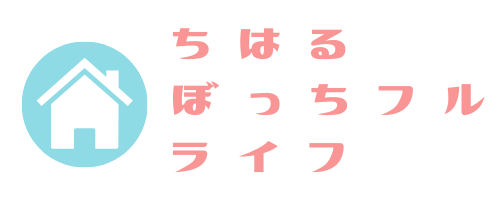
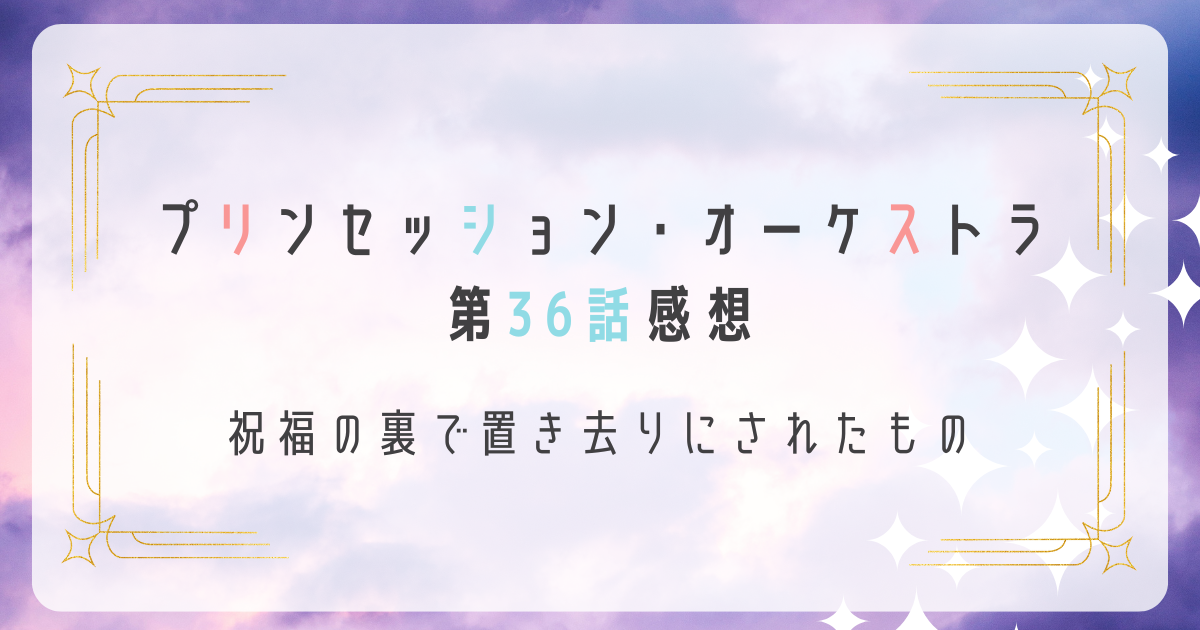
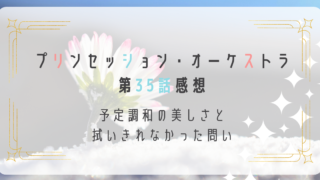
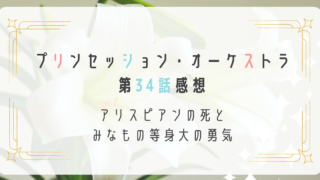
コメント